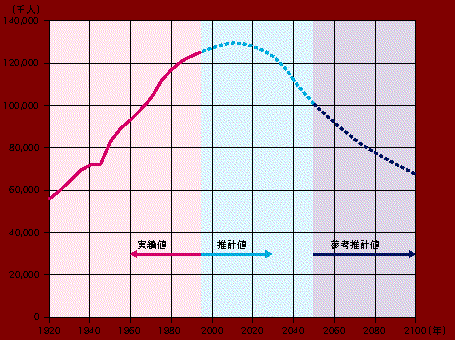
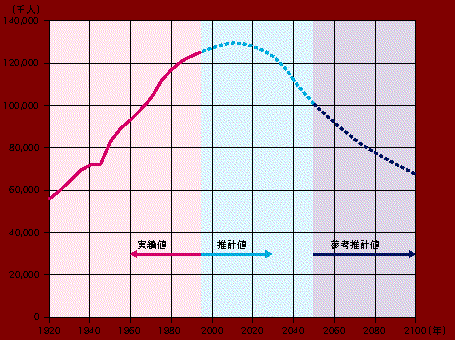
”幸福の芽” グラフで分かるように、2010年から2020年頃が高齢者が多くなると思われる。
特別養護老人ホームは本来国がやらなけれればならない事業であるが、困った人々が
なんとか幸福に生活できないものかと、小さな力であるが社会に貢献したい人々が集まっ
て奉仕しているのが社会福祉法人の姿である。70代、80代、90代の高齢者は幸福
になる権利がある。あと10年間、そっとしておいて欲しいと願っている。
戦争の為、明治、大正、昭和の時代に青春の夢を棄て、生めよ増やせよで、第1次ベビー
ブームがおとずれた。終戦後、草や木の根っこを食べ、日本の復旧に全力投球で貢献した
現高齢者が一生懸命に国の為にやった行動を、あたかも高齢社会を作ったのはあなた方の
責任だと言わんばかりに、高齢者の幸福の芽を摘うとしている。
しかも福祉施設は経営努力が足りない、市場原理の導入だと平気で厚生省もいっている。
福祉に経営など成立たない。処遇優先で利益をあげることを禁止されているのだ。利益
をあげることは不可能な事であり、福祉にそれを要求するのは、はなはだしい茶番劇だ。
”180゜転回する利用料金の違い
足音もたてずしのびより、介護、医療のどちらともつかず、正体不明の介護保険の
実施が社会福祉の基盤を切り崩そうとしている。なぜならば、介護保険適用になると
いままで収入のある人は措置費の全額、また、収入のない人は無料で、又家族負担も
あるが、本人または家族には支払いに問題がなかつた。入所者からは高いとか安いとか
にかかわらず、処遇が何故平等なのか等の苦情など全くなかった。入所者同士が
お互いにかばいあってきたのだろう。職員も差別することもなく、ひたすらに入所者の
生き甲斐の発見につとめた。しかし介護保険が導入されると、お金がない人ある人
関係なく一律(1割り負担+食事代+日用品日等)約7万円位支払いをしなければなら
ない。暫定期間として5年間の猶予があるが、現場では十分な説明も出来ず、準備指導
もできないまま突入となれば、入所者は安定していた生活の切断を余儀なくされ、行き場
がなくなり路頭に迷うだろう。また、施設も安定した処遇どころでないだろう。
”支払いの恐怖
ほとんどの入所者の年金は家族管理であり、施設に支払われる負担金は未収金となる
だろう。入所者は施設職員に支払いを請求され、払うに払えず路頭に迷い、毎日不安
をかかえ生きていかなければならない。平穏無事だったこれまでの生活から一転して、
天国と地獄を味わう様で、生きているのが申し分けないと思い、死を選ぶ入所者がでる
かもしれない。
”ごり押しの福祉 我々もそうだが、高齢者は新しい法律に理解を示すのには時間がかかるのである。
家族間のトラブルがあったり、新聞でも掲載されている介助者の虐待等で困ったとき、
老人ホームに行こうと思っただけでも高齢者には心の支えになるのである。我々が旅行に
行った時、買い物もしないのにお金があれば安心するのと同じである。つまり心の保障で
ある。市場原理が云々されているが、ホームの仕事は、食事介助、おむつ交換、入浴
介助等が95%をしめ、電源を切って休めるものではない。365日×24時間がたえず
労働時間であり、収益をだす為にはおむつの枚数を減らすか、入浴の回数を減らし水道
代、下水代、油代をうかすしか手段がなく、これらは普通の人間のすることではない。
それでは職員のパートをと、行政は言っているが、今まで行政が指導してきた介護福祉士
は、いったいなんの為だったのだろか、食事介助を例にとると、なんでもないように見え
るが、是が大変なのである。喉につまらせると窒息し、防げたとしても嚥下性肺炎になり
死亡につながるケースもある。安全と危険は紙一重である。
職員と入所者は心の糸でつながっているだけである。それを後ろから支えているのが
真のボランテイアの人たちである。
ボランテイアの人たちがいなければ行事等何もできないのが現状である。
だから福祉施設職員には食べられるだけの生活保障をした常勤の専門員が必要なのである。
” 傷ついたランクつけ
入所者の要介護のランクつけはもっての外である。集団生活しているのに、あなたは
何点、あなたは何点と入所者同士が言っていたら背筋がゾーとする。
いたわりの心があって生きるのが当たり前なのに、これが福祉の世界だろうか。
高齢の入所者にとっては要介護度はどうでもよいのだ。安らかな生活を送りたい
だけなのだ。
施設職員も介護度(お金)を気にしながら処遇はできない。
” 一石二鳥とみえるが
有料老人ホームの有利性は動かない。 つまり厚生省の狙いは民間にホームの建設をさせ、
住宅管理費を取り、介護保険を利用させ、ヘルパー派遣の導入等手厚い待遇を期待する
利用者のプライドを考え、有料老人ホームに高齢者の寝どころを確保しょうとしている。
国がやるべきホームの建設や運営に公費をつかわず、一石二鳥にみえる。これは社会の
活性化につながるよいアイデアである。しかし、必ずあてはまらない高齢者が出現し、
その高齢者は何処にも行き場がないのである。求められるのは福祉施設であり、
福祉施設はなくてはならない存在なのである。
施設入所の時は要介護度が4とランクされていたが、本人の努力は勿論、施設職員の
懸命な努力等で3カ月後には要介護度が2にランクされた。大変素晴らしい出来事で
あるが、本人と家族が喜んだのはつかの間、施設から強制的に退所命令がだされる。
家族との折り合いが悪く、虐待の恐怖から逃れたい気持ちで施設の再入所を切実に頼む
が、以前では入所できたが、要介護度2のランクでは施設経営が成立たず、心を鬼にして
入所希望者の願いを踏み躙らなければならない。経営が成立たないからと言って却下する
のが福祉施設だろうか。
魂は目で見ることができないが、しかし、日本人は魂で生きている。
介護の基本は心のケアから始まり心のケアで終わることを忘れているのではなかろうか。
好物が目の前にあったら自然に唾液がでてくるのと同じことで、人のケアは心を無視して
できるものではないのだ。
だから心のケアを専門とする福祉施設(精神・介護福祉施設)が必要なのである。
”施設の経営は
施設の経営等とうてい考えられず
福祉事業は健全な施設運営をするべきである。収入の安定がよい処遇につながるなるのは、
あたりまえである。福祉で収益をあげられるのは介護用品の販売ぐらいだろう。
”これからどうする
これからの施設運営にとって時代の流れに沿っての措置費の廃止はやむを得ないだろう。
しかし処遇低下にならない程度の定額方式にし、間違っても営利を追求するような考え方
があってはいけない。施設の機能をフル回転させ、空きベットの利用、デイサービス
365日活動、また夜間延長、介護用品の販売、厨房設備の利用、配食事業の開始、
ヘルパー派遣、入浴サービス、ショートステイ、長期入所等一環した事業をしなければ
ならない。
”遅かった社会福祉法人の経営
施設の営利追求は不可能に近いのだから、安定した経営ができるように考慮するべきだ。
が社会法人の非収益事業は、改革すべきである。なぜならば、理事報酬はなく、借金の
連帯保証人にされ割にあったものではない。いつまでも寄付金に頼る時代ではないのだ。
法人に収益事業を認め、借入金の返済も無理なくできる体質をつくるべきである。
ドイツ・スゥエーデンの昨今財政を優先するあまり、国民生活に大きな不安をいだ
かせている。 <朝日新聞 参考資料>
” 切ってはいけないザイル
介護保険は先きの見えないままの不安定状態で、目的がはっきりするまで見切り発車し
てはいけない。福祉の見切り発車は悲惨を招くだけである。
グラフで分かるようにもう少しで頂上にのぼれる。登山家がザイルを頼りに頂上をめ
ざしているのと同じで、厚生省は見切り発車で命綱のザイルを切るような行動はいけない。
1963年せっかく作った老人福祉法。苦しいけれどよじ登れ、あと一歩。その場しのぎは、
もう終わった。福祉の光を消してはいけない。切れば谷底。二度と戻れぬ。
福祉の墓場を作るだけである。真の小さな光を消してはいけない。頑張れ。
現高齢者に対しては、公的資金を導入しても国民から問題にされることはなく、
受け皿の福祉施設に対しても、誰の反対もなく理解されるだろう。
” 心豊かな福祉国家をつくりたいものだ。
(2)年齢3区分別人口割合の推移
厚生省のホームヘージより
今回の中位推計によると、年少人口の割合は、平成7(1995)年の16.0%から減少を 続け、平成15(2003)年には14.3%達する(図4)。その後も減少を続け、平成42 (2030)年には12.7%となる。以後は出生数の変動を反映してやや上昇し、平成62 (2050)年には13.1%となる。
生産年齢人口の割合は、平成7(1995)年の69.5%から平成33(2021)年の59.4%ま で減少を続ける。その後やや増加して、平成40(2028)年の値は59.6%となる。その後再 び減少傾向に入り、平成62(2050)には54.6%となる。 老年人口の割合は、平成7(1995)年の14.6%から増加し続け、平成27(2015)年の25.2 %まで急増し、その後は緩やかな増加に転じ、平成42(2030)年に28.0%に達する。その 後再び増加傾向が強まり平成61(2049)年にピークに達し、平成62(2050)年には32.3%になる。
<次をみる>