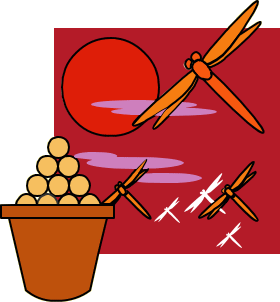


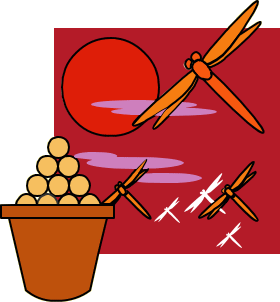




蛍袋 2010.6.7 shiro
![]()
様々に生きてきて掘る落花生
落花生ミミズ オケラも掘り起こし
羊雲休憩多いい畑仕事
女郎蜘蛛人には届かぬ網を架け
女郎蜘蛛人を惑わす紅の色
零余子ぶらぶらぶらり秋の風
女郎蜘蛛囲の中央に秋を知り
地震きて足下ふわり熟柿落つ
破られて一夜で張りし蜘蛛に秋
まとい付くはじめに蔓を引っ張って
金木犀昔に誘う香を放ち
鰯雲風が体を通り抜け
![]()
千年の香伝えて藤の花
千年藤神社つつみて香たる
千年藤みめ麗しさも昔かな
見れど飽きぬ陽を受けて皐月咲く
鶯も蛙も別尺山桜
蛙鳴く千鳥別尺山桜
ツバメとて休息もする若葉かな
散り敷いて桜の絨毯歩み入る
春耕に跳びはねミミズ虹の色
地震来る涙を洗う春の雨
風吹いてしばし見とれる花の舞

千鳥別尺山桜
![]()
昨日より今日に移りて除夜の鐘
ひれ酒に酔って撞きたる除夜の鐘
急かされて孫と撞き行く除夜の鐘
孫帰る大根白菜大和芋
土砂崩れした谷登る孫の来て
大寒や羽毛布団の中にいる
大寒や白い夜明けがやってくる
重ね着て大寒の夜が明けていく
![]()

木枯らしに木の葉の飛びし空の青
女郎蜘蛛明渡したる空の青
湯に香る冬至の柚の腹を上に
豊作の柚の香添えて海鼠食う
柚もいで日暮かけ足冬至の湯
柚の香や昔は遠し冬至の湯
枇杷の花しばらく雀遊ばせて
この冬は暖かじゃのう川光る
そりかえり木枯らしを聞く柿の枝
広島菜漬けて空気のピンと張り
コップ酒に虫酔っぱらう12月
雪虫や12月という声を聞く
南天の色と風情をヒヨが食う
風にのり雪ん子来る空の青
広島菜釣瓶落としに漬け終わる
昔ながらの石の重しに広島菜
虫食うて上手く分けあい菜を漬ける
休息は天国でせよ12月
寒波来る着れるもの皆身にまとい
取り終えし干し柿の縄風に揺れ
広島菜塩漬の香の冴えわたる
広島菜地下水くみ上げ水洗い
12月花に水やる玉光る
水滴の光りてすでに12月
水きらきら日差し優しい冬の川
落ち葉着て眠り始めし光る山
心とろとろうたた寝をする冬の山
蔦紅葉クリスマスの色に染まりけり
![]()
床の間に油虫ころぶ暑さかな
台風の脅して過ぎる恵み雨
台風の過ぎてトマトの割れ残る
かなぶんも昼間は草の上歩く
大蜘蛛を電灯照らし静かなる
1分の黙とう灼熱蝉の声
芋の葉が受けて喜ぶ水の音
一心に誠を尽くす夏の汗
充電を笑ってみてる雲の峰
充電す体かばって扇風機
![]()
花曇り余韻終わって次の鐘
風吹いてくさめして若葉山
白木蓮天衣無縫に散りにけり
耳鳴りに背中丸めて春一番
始祖鳥の末裔高き鵯の声
雪積もる瓦の形残るほど
蝋梅の香に身の固さほぐされて
夕闇に鰯の匂鬼は外
野良猫や鰯の頭もらえたか
波紋立て猫飲んでいる寒の水
土砂災害暴れし山も眠りけり
己が距離とって野良猫日向ぼ
![]()
女郎蜘蛛雪降れば巣は破れたる
広島菜青きを漬けて青き食う
なまこ食う海の暗さを凝縮す
土砂災害起きた地肌にみぞれ降る
鮟鱇の腹の中年太りかな
ふくふくの幟はためく師走かな
群雀雪の畑に柿の木に
![]()
秋に入る野良猫の目の透きとおる
雨台風ノロノロと来て動かざる
里芋の葉を太らせる雷豪雨
土砂災害里芋の葉は伸び放題
水滴をこぼし芋の葉ゆらり揺れ
熟れた柿から落ちて日の強し
白菜や虫食い良品貰われて
女郎蜘蛛化粧そろそろ秋の空
釣瓶落とし影のみせわしく動きけり
落ち葉舞う釣瓶落としの影動く
切れし紐軒に残して釣瓶落とし
叙勲には縁がなくして秋耕す
女郎蜘蛛空き巣を雄が守りおり
女郎蜘蛛巣に雄残り木枯らしや
般若心経に挑戦 その3
そろそろこの章でまとめなくてはなりません。
人の優劣はだれが決めたのですか。人が決めたのであれば偏見もあるし、人は神の世界など分か
りませんが、神が決めたのであれば偏見などありません。
私たちはこの世にある役目を持って生れてきたとしか考えられません。この世に生を受け
ほんのわずかしか生きられなくても、100歳まで生きても価値は同等と考えます。
人の生き死にはどうしようもありませんが、神の世界では決まっているのかも知れません。
運命はきまっているように見えても、現に私たちはしようと思うことはすることができます。
私たちはこの世に何をしに来たのでしょうか。
良いこと悪いことを経験し、自分自身で考え、修行するために来たのではないでしょうか。
「貪・瞋・痴」(煩悩)を持った人間は善と悪をその中に抱え込んでいます。抱え込んだ
「貪・瞋・痴」をなくすための修行をしています。その修業は死ぬるまで終わりません。
悩みながら自分の進むべき道を見つけることが大切です。自分を見つめながら、内省する。
そうすれば自分の愚かさとか欲というものが見えてきます。
仏法の根本教理に次の3つがあると書かれています。
1.
諸行無常‐‐‐あらゆるものは移り変わる
2.
諸法無我‐‐‐あらゆるものは実体がない
3.
涅槃寂静‐‐‐心のやすらぎこそ真の幸せである
人間は知恵であれこれ分別し、迷ったり苦しんだりしている。金、財産、地位、名誉、生命
などこの世で大切と思っているものは生滅をくりかえします。
人の一生は死をもって完了します。いくら残した金や仕事があっても、それで完成です。
なぜ神は不完全な人間をこの世に送り出したのでしょうか。
これは仏教でもキリスト教でも行き当たる問題です。釈迦もキリストもこの世に生まれ、
生きるということ体験し、色々なことを体験し、人間として修行し、死んでいかれました。
不完全な人間が善と悪とを体験し、学ぶということをしているとしか考えられません。
それならば、不幸なときからも、幸福なときからも学べます。
修業とは煩悩をなくすための修行です。生き変わり死に代わり煩悩をなくす修業をしている
のかもしれません。一生は節目のようなものかもしれません。
神と人の違いは神には煩悩がなく、人は煩悩を持っています。煩悩とは無明と渇愛(欲)です。
般若心経の中に「照見五蘊皆空 度一切苦厄」というところがあります。
(五蘊・・・色・受・想・行・識の5つのものが集積されてできあがった、心身のことです)
これは「身も心も空であることを悟られ、一切の苦しみから救われる道を示された」というと
ころに大きな意味があります。観音さまが行(ぎょう)をされ、人の苦しみを救うことを悟ら
れた内容です。移り変わり、実体がないものに悩んでも仕方ない、煩悩を抑えれば心の安らぎが得られる。
これが仏法の根本教理であったのです。
その後「色不異空 空不異色 色即是空 空即是色」というのが出てきます。五蘊が空なら、
五蘊の中に色が入っていますので、色も空です。
その訳が「形あるものは空であり、空なるものが形あるものを構成している。したがって形あ
るものはすべて空であり、空がもろもろの形あるものになっている」
味わいのある言葉であり、うまい訳だと思います。
空が形あるものを構成しているとは、砂上の楼閣とか、蜃気楼のようなはかなさがあります。
人間の体すらも実体がなく、悩むに値しない。まして、金、財産、名誉など悩むに値しないもの
である。新しいものは古くなり、名誉、肩書きなどはすぐに衰えてしまう。
ここらで少しまとめてみると、「移り変わる、実体がない」ものを追わず、「心の安らぎ」を
を得ることが幸せになる道であるということです。
なぜできないのでしょうか。何度も言ってきましたが、煩悩があるからです。
引用文:「般若心経のすべて」 公方俊良 著
「仏教の教えで一番大切なところは、自己を見つめ内省をするところにある。そうすれば
自分の愚かさと欲という煩悩が見えてくる。煩悩を空じ、心にとらわれがなくなれば、業の
障りから解放されるので、因果にとらわれることがなくなり、あるがままに生きることができる。」
煩悩を空じ尽くしていくことは簡単なようで、大変難しいことである。
例えば金や財産、家族や学歴など、今まで自分が「ある」と思い、持っていることを徹底的に
否定し、捨て去ろうと思っても、そこに捨てきれない愚かな自分が見えてくる。
そこで初めて、自らの愚かさと欲にきずき、内省して、迷いの中から無心に生きるやすらぎを
見出せるのである。このことを、煩悩即菩提、煩悩即涅槃という。
つまり、迷いがあるから目覚めがあり、やすらぎが得られるのです。
煩悩をなくせれば私たちは何もとらわれることのない心のやすらぎを得ることができ、幸せに
暮らせることができるのです。
それには、貪りを抑え、瞋(いかり)を抑え、愚痴を少なくしていくより仕方がありません。
すぐにはできなくても、毎日少しずつ心掛ければできるようになるかもしれません。
人は絶頂期にある時はそれが当たり前だと思い、なかなか煩悩を抑えることができません。
苦しかった時のことを思い、頑張るしかありません。
煩悩というものは実体のない幻に惑わされているに過ぎず、いつも心は波打っているのです。
一度心のやすらぎを経験すれば、少しずつ欲から離れていくことができるようになるかもしれません。
イソップ物語で都会の生活にあこがれたネズミが、都会に出て行き、都会のネズミの生活を体験します。
いくらいいものが食べられ、いいところに住もうが、いつもびくびくとした生活
田舎の生活がいいと言って戻っていくところがあります。
心のやすらぎということを考えますと、少しくらい物が足らないところがあっても我慢できるのでは
ないでしょうか。
高望みをせず、現在の生活を続けながら、欲望(貪・瞋・痴)を抑えて行けば、心の安らぎが得られる
生活ができるのではないでしょうか。
これから先のことは分かりませんが、老後を立派な高齢者の施設に入って、認知症で長生きするよりは、
野垂れ死にでも心おだやかに暮らせる生活がいいと思うようになりました。
奥の細道に出発した芭蕉が目指したものは、心の幸せであり、たとえ野垂れ死にしても望んでいたことか
もしれません。
私たちはどういう生き方でも選ぶ自由があります。何不自由のない生活を選ぶことも、貧しくても心豊か
な生活を送ることもできます。ところが、何不自由もない生活と、心豊かな生活というものを2つ持つこと
は極めて難しいと思います。
私たちは日本という大変恵まれた環境の中で生活し、衣食住、高望みをしなければすべて
足りています。私は感謝しながら生きていこうと思います。
最後は、なんだかめでたし、めでたしということになってきました。
般若心経に挑戦 その2
叶谷 史郎
人間は不安定な大地の上に生きています。どういう災害に遭うかもしれませんし、いつ
死ぬるかもわかりません。こういうことを考えていたのでは心の休まる時がありません。
良寛さんのように「災害に遭う時には災害に遭うのがよろしく、死ぬと時節は死ぬのが
よく候」という覚悟があればいつも心静かでいられます。
これが般若心経の「照見五蘊皆空 度一切苦厄」で、心に引っかかるものがないと、一切の
苦しみから救われるということでしょう。我々凡人にはそうはいきません。
地震がすべての財産を奪うかもしれませんし、最愛の家族を奪うかもしれません。楽しい時
はほんのわずかで、苦しみの時間は長い。仏教では「人生は苦しみ」ととらえています。
健康な体はいつか衰え、楽しい生活もいつかはなくなってしまいます。時間がすべてを変化
させます。留まりたくてもそこにとどまることはできません。
私たちは時間を止めることはできません。平家物語の「驕れるもの久しからず、ただ春の夜
の夢のごとし」で、平家も源氏も一世を風靡して滅んでしまいました。
信長、秀吉、家康も同じです。時の流れとともにすべてが変化する。それがこの世のさだめです。
時代の流れについていかないと一人が取り残されてしまいます。
そんな中で人はどのように生きればいいのか。私たちは幸せに生きたいという望みがあります。
しかし幸せは追っかけて行って捕まえることはできません。
生きている現在が一番幸せなのである。しかし人は現在の幸せを幸せとは感じていません。
幸福の青い鳥、山を越えると幸せがあると思っています。
現在の幸せを感じて生きているものだけが、幸せなのである。幸せを求めてたどり着く先は
滅びた王国なのです。
般若心経を読んでいくと、幸せは心の中にあり、それを感じる人だけが幸せなのだというこ
とが分かってきました。
心で幸せを感じなければ、海外旅行に行こうと、三ツ星レストランで最高の食事をしようと、
幸せなどありません。
年をとるということは死に近づいていますから、だんだん体も弱ってきていきます。
美しかった顔にもしわがより、澄んでいた瞳も濁ってきます。
「人生が苦しみ」というとらえ方をすれば、死は苦しみからの解放ととらえることができます。
死ぬるのが嫌だといってもこれから逃れることはできません。
お迎えが来たことを感謝しなくてはなりません。死というとどうしても暗い話のような気がして、
あまり触れたくありませんが、死を考えることによって生きていることが何て素晴らしいかという
こともわかってきます。光と影のようなものです。
死を考えることによって、なぜ自分がこの世に生まれてきたかが分かるかもしれません。
般若心経を読んでいると仏教の奥深さが少しわかったような気になります。
世間では孤独死、孤独死といって問題にしていますが、孤独死も立派な死です。何も病院で
医者に守られながら死を迎えるのがいいとも限りません。
私たちは事故に遭っても死んでしまいますし、病気でも死んでしまいます。遭遇する環境でどうし
ょうもない死を迎えることだって起こります。
長生きした人が素晴らしく、早く死んだ人は劣っているということもありません。
人は平等に生まれてきたわけではありませんから、ノーベル賞をもらった人が立派で、ただの百姓
は人間的に劣っているということもありません。
ただ、あらゆる種類の人がこの世界に生きていて、人間的な優劣はつけられません。
それではどんな人が素晴らしいのですか。それは与えられた環境の中で黙々と生きている人ではな
いでしょうか。人はこの世にある使命を持って生まれてきて、死んでしまえば使命もお終いという
ことになります。多分、天国に行けるのでしょう。
私たちの生きている世界には時が存在し、時がたつほど進歩していっているかということに対しては
何もわかってはいません。確かに科学は進歩していて、色々な分野で花が開いているように見えます。
それでは科学の進歩が人間に幸福をもたらしているかというと疑問があります。御釈迦さんが生きて
いた時代から時が流れて宗教は進歩したかというと、これまた疑問があります。宗教は進歩しなくて
もいいのでしょうか。
宗教の目的は人を幸せにすることであるなら、もうそろそろすべての人類は幸せになってもいいはず
なのに、そのような実感はありません。ますます悪くなってきているような気がします。良くも悪く
もそれは仏教には関係ありません。仏教に対する人間の姿勢の在り方です。
まじめに取り組めば、それなりの結果は期待できるのかもわかりません。
渡辺和子著「面倒だから、しよう」を読んで、キリスト教と仏教は本当によく似たところがあるのだ
と思いました。さすが、世界の二大宗教です。
この本から引用してみます
l 価値があるから生きるのではない。生きているから価値がある
l この世に雑用という名の用はない。用を雑にしたとき雑用は生まれる
l 愛想が尽きるような自分を見捨てないこと
l 当たり前のことがありがたいものだと気付けば、幸せの度合いは高まる
l ふがいない自分を受け入れ、機嫌良く感謝を忘れずに生きる
l 自分の言い分を少し抑え、まず相手の気持ちをうけとめる
l 自分がされて嬉しかったことは、ほかのひとにもする
l 不親切でなくとも親切さに欠ける自分に気付く
仏教やキリスト教を信仰するということは大切です。
「般若波羅蜜多」の中の般若は知恵、波羅蜜多は完成です。知恵だけで駄目で、知恵と仏教
が結び付かないと本物になりません。ギリシャ文明は素晴らしい知恵の文明でした。
しかし、アレキサンダー大王は東はインド、西はユダヤを征服したのですが、ヘレニズム文明は
インドでは仏教に、ユダヤではキリスト教に思想的に敗北したということになっています。
ギリシャの知恵だけの文明が仏教やキリスト教に思想で負けたということは人間の弱さを物語っています。
知恵と宗教が結びついて初めて完成があると思います。宗教は人間の欠けているところを
補う何かを持っているような気がします。
人間は科学の恩恵は沢山受けていますが、科学だけでは生きていけないのです。いくらいい望遠鏡が
あっても、人間の生き方は教えてくれません。
10冊は以下の通りです
⑥般若心経:島田 裕巳著 ⑦ほっとする良寛さんの般若心経 :加藤僖一
⑧般若心経を読み解く:藤原 東演 ⑨般若心経90の知恵 公方 俊良 ⑩生きて死ぬ智慧
般若心経に挑戦 その1
叶谷 史郎
般若心経を自分で分るように理解してみたいと思うようになりました。
般若心経の翻訳本は沢山あるので、10冊くらい読めばできるのではないかと気軽に考えて
の出発でした。先ず、最初に読んだのが 鎌田茂雄著 「般若心経講話」でした。
一度読んで感じたことは分るところは分かるが、分解からないところはあまりよくわから
ないということでした。もう一度読んで、これは言葉の解釈よりも、思想が分からなければ
理解できないということが分りました。般若心経というのは262字に膨大な「大般若経」
600巻の内容を圧縮したものということです。「般若心経」は目で読むのではなく、心で
読むものであると書かれています。「般若心経」の解釈書を読んでも、心で読まないとな
かなか理解できないところもでてきます。分からないところは勝手読みをしてしまいます。
初めからある程度困難は覚悟の上で始めたので、このくらいのことであきらめるわけには
いきません。先ずは目で読んでみて、全体の意味をつかんで、考えていかなくてはならな
りません。自分の心に残るところに印をつけ、読み進めることにしました。
ここで前にたちはだかる断崖絶壁のようなものを感じました。
有名な「色即是空」「空即是色」の解釈は「物質は空であり、空は物質である」と訳しても
意味は分からない。アインシュタインの相対性理論でも物質がゼロになることはない。
禅のむつかしい公案のようである。読み進めていくと分かるようになるのでしょうか。
般若心経の講話をする著者もわかり易く書いているのだが、素人にはなかなか分りにくい。
ある時、何かのきっかけで、もつれた糸が解け出すのを期待して読み進めることにしました。
表題の「摩訶般若波羅蜜多心経」の波羅蜜多とは到彼岸ということで、「悟る」という
意味です。大乗仏教は自分が悟るより先に他人を先に到彼岸させることを説いています。
私たち凡人は他を利すれば、自分を利することにならないと考えます。
引用文
“他を利する行為は自らをも利する。他を利することは「みずからが力を分かつ」ことなのである。
おのれの分限に応じて、その力を分かつことは、己れ自信を拡大していくことになる。
己れ自信を心豊かにしていくことになる。報酬を求めざる無償の行為には跡がない。
わざとらしさがない。そこはどこまでも透明な空間である。我々凡人にはとてもこのような行為がで
きるものではない。われわれにできないからといって、そのようなそのような世界が存在しないとい
うのは、心の驕(おご)りにほかならぬ。“
このことはボランティアの考え方そのままです。人のためにボランティアしていると思えば、
ボランティアは続かない。大きな意味で自分のためになることが、人のためになっていると
考えればボランティアも長続きしそうです。いい文章に出会いました。自分のためだと思っ
てボランティアしましょう。
「五蘊皆空 度一切苦厄」
観音さまがお見通になられ、永遠不変なるものはないといわれた。自分の肉体も家族も、
自分の所有物も何一つ永遠不滅なものがなく、すべて空である。これを理解すればすべての
苦しみから救われるということがわかったのです。ここが大切なところです。
引用文
“人生やることなすこと全て苦と見れば、苦でないものはないし、楽と思えば楽になる。
人によって苦に感じることも、他の人は楽に感じる。要するに苦楽などいう実体はない。
自分で苦と思うから苦、苦と思わなければ苦でない。楽と思えば楽なのだ。我々の生活を
苦と思うのも楽と思うのも心の持ちよう一つである。この肉体が空だと分れば、すべての
苦しみから脱せられると観音さんはお見通しておられる。“
これが五蘊皆空です。全てが空なら苦しみは起こらないということです。
「観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時」観音さんが到彼岸の修行をしたとかかれています。
行とは三毒をなくす修行のことです。三毒とは貪瞋痴(トンジンチ)です。
「貪」はもと欲しい、もっと欲しいという貪りの心です。「瞋」とは怒りで、かあっとなることです。
「痴」とは字のごとく愚かなことで、自分は賢いと思い、独りよがりになってしまいます。
人間は完全な人はいません。常にこの世で修行をしているのです。どんな偉い人もなかなか三毒から
離れることはできません。
絶好調のとき危ないのです。なんと人間は不完全なのだろうかと思います。不完全だからこの世で修行する。
修行というものは楽しいはずはありません。だから、「人生は苦である」となります。
人生は悩みなど無くなりません。ひとつ悩みがなくなったと思ったら、次から次へと悩み、苦しみはでてくる。
のサイクルから抜け出さなくてはなりません。
そのためには修行して三毒から離れなくてはなりません。禅寺に行って、座禅しながら「無、無、無」
といいながら修行しなくてはなりません。とてもできませんし、修行したからといって、三毒からぬけ
だせるかどうかもわかりません。
凡人は悩みながら、苦るしみなが生きることになります。しかし、苦楽に実体がないということが救いで、
苦と思わなければ苦でないのですから、ひょっとしたら楽しく生きられるかもしれません。ちょっと待って
ください。悩みも、苦しみもない人生って、楽しいでしょうか。妻と私は認知症のお母さんを介護していました。
欲もなくなり、食べ物すら食べようと
顔が穏やかになり、黙って座っておられました。こうなるともう人間ではありません。
苦しみも、楽しみも何も感じなくなっているようでした。
例えば、苦労して、苦労して入学試験に合格すれば飛び上がるほどうれしいはずです。
苦楽はあざなえる縄の如しで、苦の後に楽がやってきます。だから生きておれるのです。
ちょっと脱線しました。
いま私は5冊目の「新訳 般若心経」 松原哲明著 を読んでいます。
② 般若心経のすべて 公方俊良著 ③ 現代語訳 般若心経 玄侑宗久著
④ 寂聴 般若心経 瀬戸内寂聴 著
般若心経を理解するより、むしろバックグランドの四苦、八苦、四諦などの説明に時間がかけられていて、
般若心経の実態にはなかなか迫るところまでいきません。
難しいことをいっても解からないのでこういうことになるのだとおもいます。
「人生は苦なり」が仏教の基本で、苦しむ衆生を救おうとする観世音菩薩がおられ、観音さまを信じれば
救われるのに、人は観音さまを信じることができない。
これはキリスト教でも同じことで、イエスキリストを信じれば苦しみから救われるのに、人は信じること
ができないで苦しんでいる。
なぜ信じることができないか。煩悩や無明が邪魔するからである。邪魔する無明や煩悩を取り除くのが
修行である。また座禅で「無、無」に戻ってきました。
やはり凡人は苦しみを背負って生きなくてはなりません。
家康の遺訓 「人生は重き荷を負いて遠き道を行くが如し。急ぐべからず。不自由を常とおもへばふそくなし。
心に望みおこらば困窮したる時を思い出すべし。・・・・・」
過去を振り返ってみてください。苦しみは全て消され、あの頃はよかったと思いませんか。
そうです、振り返ってみれば、いつでも今が一番いいはずなのです。
苦しいと考えず、今が一番いいと考え、前向きに人生を生きていきましょう。
般若心経の訳本を読みながらいつも脱線しているのに気が付きます。脱線もいいではないですか、
結論を急いでも空ですから、時々は色をつける必要があります。
人間はもともと不平等に生まれています。それが最後には死んでいきます。
最後も誰が勝者で誰が敗者ということもありません。それは全てお見通しの神様が決められることなのです。
あえて勝敗をつけるとすれば自分のおかれた環境の中で、すこし前向きに生きた人が勝者かもしれませんし、
もともと勝敗などはつけられない問題だと思います。
好きな文章を見つけて楽しみながら、仏教を学んでいこうと思います。まだ5冊目ですから、
もう少し読み進めてみたいと思います。
![]()
打ちし蚊の手足が動く新聞紙
土石流難逃れ寄る蟷螂も
土石流箱庭崩しの家も木も
台風の雨に残りし胡瓜取る
台風の去って透明山や川
ズワイガニ店頭で吹くあわ白し
生か死か蜘蛛の巣一夜で張り替えし
払われて一夜で張り替え女郎蜘蛛
まだまだと庭木を切って歳を知り
![]()
夏が来る子の顔を見る母の顔
天啓の如くに揚羽前よぎる
ぎぼうしの咲き乱されて梅雨終わる
青柿の見る間に太り枝の先
青柿の落ちて転びし表裏
蜂の巣を2つ残して剪定す
灼熱の大地に青きかりんの実
夏祭り浴衣にあふれる若さかな
地上に出ミミズからから大暑かな
緑陰に蜂は大暑の水を飲む
台風の去って涼風肌さする
蝶も蜂も影を潜めし草いきれ
台風は何事もなく川すめり
猫の子の死臭漂う天の川
蠅たかる子猫弔う猫親子
夏草を掘って埋めたる子猫の死
七夕や巨大キューリに雨が降る
![]()
畑を打ち草燃す煙 薯の花
五月雨や巣の中央に蜘蛛ぬれて
春の山明るすぎたる棺かな
山萌えて青不動住む山に入る
豪華さやジャーマンアイリス枯れかかる
葉脈を透かす日差しや青嵐
73年生きた体に若葉かな
色即是空萌えいずる山空なるや
若葉萌え幼子の目は何を見る
全身に萌える青葉の風を吸い
庭木切る翅ふるわせて脅す蜂
月光の差し込む部屋の春や春
月光に文字書きおれば喧嘩猫
![]()

ひともとの枝垂れ桜に人集う
窓開けて入る春風が通り抜け
白木蓮純白のまま留まれず
桜吹雪天地の間に佇めり
桜吹雪車は花びら巻上げて
難関を越えれば山あり新芽ふく
桜散る烏ピョンピョン忙しい
常緑の青の隙間を若葉埋め
柿若葉香りがあれば吸い込んで
白い歯を見せて笑う子柿若葉
萌えいずる若葉の息吹背を伸ばす
見渡す限り若葉魔法の杖
春日長毛虫ブラブラ風任せ
春の夢見せてくれたる布団畳む
恵み感謝春草は花咲かす
ダイヤモンドダストのように舞う桜
桜散るひらりひらひら風に乗り
亡くなりし人の表札桜散る
原木の椎茸重し春の雨
![]()
春一番鍬が蛙の目を覚ます
春耕や眠い蛙が掘り出され
捨てられし子猫に春は訪れし
寄り添って冬越す子猫に春一番
花粉黄砂供に従え春一番
子猫死ぬマッチ売りの少女かな
春の雨金木犀は雀宿
白菜を割って菜の花出番なり
![]()

ヤマトイモ土の臭いの中に掘る
傷なしに山芋を掘る雪もよい
発掘を楽しむようにヤマトイモ
ヤマトイモ掘る横で猫覗き込み
草虱いずこで付き散歩道
陣笠のような椎茸年始め
鮟鱇の開いた口より欝を吐く
むずかる子抱いて立ち去る大晦日
捨て猫に正月はあり毛づくろい
正月の本抱え込み孫の勝ち
頂に薄雪かむる我が頭
寒波来る気合を入れて起き上がる

![]()
飛行雲山越えてくる渡り鳥
心臓の音の聞こえる夜の冷え
煌めきてやがて寂しき冬銀河
木枯しや病院の長き待ち時間
赤と青色で差別の青海鼠
紅葉の終わりし頃の庭紅葉
捨て猫の日だまりデビュー落ち葉散る
子猫4匹冬の太陽を独占し
動かぬ首回してみても皆紅葉

![]()
稲実る中に幟や奉寄進
秋日受け砂の上這う蝸牛
町めぐり終わりの火の粉秋の空
ひょっとこの顔大写し秋祭り
台風の雨に湿りし靴の底
17期会旅行
秋の旅海の青さを笑いけり
琴平の夜長を笑う宴かな
台風に急かされ帰るしまなみを
熟柿落ちひよどり鳴いて路地に消え
子の顔に手をかざす母時雨かな
釣瓶落とし負けじとばかり畑を打つ
木枯しや1番2番と山を染め
山芋を掘って山辺の空赤し
韓国チェジュ島の旅 H25.4/7~4/9
韓国の済州島に3日間のツアーで妻と一緒に行きました。済州島は火山活動で出来た島で、玄武岩で覆われています。
島の人は観光と農業、漁業に携わっていると聞きました。農業するにも土木工事をするにも火山島ということで岩の
処理が大変だそうです。掘り起こされた玄武岩が畑の境に積まれ、風除けの役目をしているそうです。
済州島を表す言葉として「三麗」「三多」「三無」といわれるそうです。
三麗・・・「美しい心」「すばらしい自然」「美味しい果物」
三多・・・「風」「石」「美人」
三無・・・「泥棒」「門」「乞食」
「三多」の風は海の中の島で風が強く、火山島で黒っぽい石がごろごろ、美人は言い過ぎかもわかりませんが、
女性が多く、よく働くということだそうです。海女になって海にもぐったり、農業で畑を耕したりしている一方、
男は昼間から酒を飲んで、博打をして、気位が強く、働かないそうです。だから奥さんには頭が上がらないのでしょう。
男が強いのは戦争があるときで、女が強いのは平和なときといえるかもしれません。


三無は泥棒や乞食をしないでもいいように島が豊かで、女性が良く働くのです。門がないのは泥棒
がいないので門が要らないということなのです。もう一つは韓国の人は気位が高く、乞食や泥棒をす
るくらいなら、働いた方がいいという考えがあるようです。私は韓国のバスに乗って島を移動するとき、
日本車を全然見かけなかったのは不思議だと思いました。
車のタイヤも日本製は見つけることができませんでした。韓国は外国の自動車を何らかの形で入れないよ
うにしているのかもしれません。もう一つ軽自動車が少ないのにも驚きました。
ツアー客の一人がなぜ韓国には軽自動車が少ないのですかとバスガイドさんに質問しました。
答えは「気位が高いからです」ということでした。軽自動車に乗った人は一段低く見られるのだそうです。
日本ではエコカー志向でハイブリッドや軽自動車が増えています。私は気位が高いということは大事なよ
うな気がしてきました。乞食や泥棒いなくなるのなら、これは大事ですし、日本の「武士道」に通ずると
ころがあるような気がしました。金や経済ばかり追っかけていくとエコノミックアニマルにまで成り下がります。
済州島の気候と日本の気候はよく似ていて、広島で着ていった服装そのままで通用します。
島をバスで移動しているとき、岩場で漁をしている海女さんが見えました。
済州島の海女さんは優秀で、日本から海女さんの実習に来ている人もいるぐらいだそうです。
朝の連続テレビ「あまちゃん」で若い海女さんがいなくて、年寄りの海女さんばかりが頑張っている
姿が写りますが、ここでは伝統が引き継がれ、かなりの海女さんが活躍されているということでした。
日本では海女さんみたいな辛くて、しんどい仕事はなり手がなく、高齢の海女さんがいなくなれば海女さんの
伝統が途切れてしまうところまできているのではないかと思います。済州島の女性は良く働くので、海女さんの
伝統は引き継がれているのかなーと思って聞いていました。島にはトルハルバンという石像がたくさん立っていて、
これが島の守護神として崇められています。素朴な顔をしていて、モアイ像とよく似ています。大きなトルハルバン
があったので覗いてみると電話ボックスでした。島では韓国映画のロケ地も立派な観光資源です。
ドラマ「オールイン」の修道院を再現した記念館とか、「チャングム」のお産した洞窟なども観光バスは行きます。
観光地を廻った後で立ち寄るのがお土産売り場とか免税店です。
革製品、紫水晶、化粧品、薬草とかサプリメントの類です。
化粧品など効果はよく分からないのですが、バスガイドさんが言葉巧みに宣伝され、
「私も何年前から使っていて、こんなに肌がきれいになりました」とか「これを使うと他の化粧水は要りません」
など言葉巧みに宣伝されると、いい年のおばさんなど惜しげもなく買われます。茅葺の民族村では、民族村の女性が
日本語で面白おかしく生活の一部を紹介し、聞いていると「日本の吉本」に出ても引けをとらないくらいの巧みさで
人を笑わせていました。
大きな水がめを持った女性の石像の前では「済州島の女性は重い水がめを運んで重い。
だからお母さんのことをオモニといいます」とか、黒豚の豚舎では「黒豚は人のウンチを食べて味が良くなる」
とか言って笑いを誘います。
最後に薬草の甕の前に連れて行き、こうして薬草を醗酵させたエキスを飲むと「血液がさらさらになり、
病気をしなくなる。だからこの村は長寿が多く、年をとっても元気です」となる。エキスを薄めたものを
みんなに飲ませ、商売が始まる。私もこの薬草のエキスを1本3,000円で買って帰り、せっせと飲んでいる。
効くと思えば効いた様な気もする。
気候がよく似ている済州島(チェジュ島)の人と、日本人はよく似ているなと思うと段々韓国が遠い
国ではなくなってきた。
食事は骨付きかルビの焼肉、黒豚プルコギ、海鮮トッペギとアワビのバター焼きにキムチを食べ、
ビール、マッコリを飲み、段々と韓国料理の美味しさが分りかけて来た。
韓国の人は料理を作るのに時間をかけ、食べることを楽しみ、食べることにより病気を治していく
という考えを持っているようです。
韓国映画「チャングム」も宮廷料理を扱っていた。食事を薬のように思っている。
韓国といえば今まであまり見て見ないふりをしていたのが、段々と魅力のある隣人のように思えてきた。
日本より古い文化をもち、囲碁にしろ、ハイテク技術の電化製品などよきライバル、良き隣人として付き
合っていけるのではないかという可能性を見つけることができたような気になってきました。
韓国の観光事情は段々と日本からの観光客が減って、中国からの観光客が増えつつあるそうです。
「日本語を話す観光ガイド人は失業者になるので、日本の皆さん韓国に来てください」
とお願いしていました。竹島の問題、慰安婦問題、靖国神社参拝や歴史の教科書など韓国との間は
ギクシャクしてすっきりしていない。
日露戦争の頃、韓国が日本の植民地になったり、太平洋戦争中も韓国の人は日本人にひどい扱いを
受けたという意識があって、韓国の人も日本人とすぐには仲良くなれない。
仲良くなるには時間が必要です。少しづつわだかまりが解け、仲良くなれるのはいつのことに成るのでしょうか。
 |
 |
龍頭岩
電話ボックス
![]()
短歌
確実に朝の光は届きおり点滴つづく私のもとに
空が白くなってきて、夜が明けてきたと思いました。なんだか
希望の朝がやってくるような気がしました。
この気持ちをまとめてみようとしたら、短歌になりました。
俳句 (病室)
熱帯夜夜明けの白き光満つ
汗の臭う病室にいる朝あかり
悲しみが人にまつわる雲の峰
点滴2本急かされている残暑かな
汗が臭う小便が臭う泌尿器科
入院の余白を埋めし甲子園
退院で娑婆には出たが猛暑なり
病室に笑顔たやさぬ蓮の花
汗臭う退院の日の枕かな
入院す昔河鹿の鳴く川辺
炎天に涼風と来て揚羽舞う
雀来て揚羽来て炎天のプラットホーム
原爆忌蝉の鳴き声か耳鳴りか
原爆忌時の止まりし命たち
![]()
ツバメの子声の大きな子が育つ
深みへと人を誘いし鮎の川
三毒を押さえ抑えて大暑かな
我慢しろいえぬ暑さや親が子に
夏草を抜く迫力に蚊が寄らず
夏ばての人に浅利が潮を吹き
蝸牛芭蕉のような旅夢見
生きていること確かなる汗がある
炎天や獣流しし血の乾く
鳴きながら一筋に澄む蝉の声
炎天や選挙ポスター笑い泣き
炎天や青とかげの子は青とかげ
飛び出して子蜥蜴の尾の青さかな
ランナーに命をつなぐ次郎三郎
遣り遂げて死ねたら極楽蝉の声
遺言をどういて鳴く蝉の声
打診して買わぬ西瓜に実る音
張り裂けんばかりの西瓜音を聞く
青とかげ走り過ぎたる後に虹
炎天や枯れていくもの伸びる蔓
陽炎の立つ中電車着て止まる
歩かれぬ足炎天の車いす
母の愛日陰大暑の乳母車
蝉鳴かぬ時刻にありて昼寝する
また朝の平和を告げる蝉が鳴く
倒れれてたまるかアスファルト臭いむんむん
![]()
艶やかの限りつくして牡丹散る
杖とりて心決まりし春の山
春風にのって蝶来て蝶さりぬ
子を連れた鹿に出会って見張られて
見る人もなくて盛りの藤の花
うぐいすの鳴き声半端山笑う
山頂は椿の盛り城の石
ああいうのもいたこういうのもいた茄子の花
よみがえる蛍に夢の大いなる
川風に誘われ来しに蛍2匹
蛍帰る白髪頭にいつかなり
蜂の威をかわして青き枝を切る
ペットボトル夏の太鼓に震えだす
渾身の太鼓震わす青葉若葉
原爆ドーム青葉若葉の炎立つ
そら豆や茹りて箸を通しけり
ねずみより大きな子猫納屋かける
4匹の子猫育てて退かず
![]()

じゃが芋の芽掻き無常や1本に
霧島の古木全身花まとい
鍬の先かわして蛙掘り出され
三寒四温枝垂桜の散り兼ねつ
四月馬鹿満開の桜散り初める
葱坊主唯我独尊蝶招く
啄木鳥の聞こえてくるよ春の音
春の土雑草抜かれまた抜かれ
早く来いじゃが芋の芽が呼んでいる
そら豆の蝶を集めて日の長し
5分咲きの桜に雪が興を添え
日は移り色移り皐散る

人の来ぬ部屋の時計の日の長き
ぼうたんをささえる首の重し重し
ぼうたんの色香に迷い蝶の死ぬ
牡丹揺れ光が揺れる人揺れる
春電車ごとんと揺れて本が落ち
山笑う読みかけの本落としたり
鍬で土を耕していると冬眠中の変えるが飛び出してきました。
おそらく蛙はびっくりしたことでしょう。
![]()
徒手空拳で来て桜かな
胸のふくらみはちきれんばかりの桜かな
焚き火して迎えてくれし皺の顔
大根の白と黄色の花が咲く
鍬の先逃れでてきた殿様蛙
冬眠の蛙春眠掘り出され
紅茶舞う自然の深さ春たちぬ
ヒヨ鳴いてじゃが芋の芽は土の中
天きまま春の嵐に倒れ花
ヒヨ鶫桜のトンネル通り抜け
ヒヨ鳴いて若芽の出る香りのす
白木蓮黄砂一粒寄せ付けず
白木蓮光集めて影のなし
![]()
恋猫のなく声おろか夜の冷え
寒夜なく猫苦しみを知り尽くし
薄明かり海鼠(なまこ)の孤独噛みしめて
水仙の咲いて光を集めおり
啼いてきて啼いて去り行く鵯(ヒヨ)の声
理不尽な冬眠蛙掘り起こし
霜柱踏んで行かねば進まれず
寺またぎはかなく清き冬の虹
大根の地上が伸びる2月かな
着ぶくれてそこのけそこのけ酔っぱらい
寒波来るまあるくまあるく床の中
冬の欝(うつ)負けそうになり畑を打つ
春の草主役はキャベツ言って抜く
![]()
三が日初夢も見ず眠りけり
新年の手帳に予定記しけり
三が日夜更かしの癖抜けきらず
新年の壁に仏のカレンダー
しめ縄の稲穂に雀三が日
孫の来る妻の頭は孫ばかり
孫が来る背に足してやるお年玉
![]()
クリスマス
一つ二つ足らぬものありクリスマス
みかん箱いっぱいの幸福届きたる
クリスマス靴をはみ出す贈り物
雪かぶり霜にあい白菜甘み増す
風花や心の隙間に迷い込み
風花やホワイトクリスマスには遠くとも
風花や北の風には横に舞い
蟷螂 かまきり
たうろう 鎌切 斧虫 いぼむしり
カマキリ科の昆虫の総称
3.jpg)
蟷螂の鎌なめている日向かな
蟷螂を日向に移す動かない
冬至過ぎ蟷螂の動きロボットに
蟷螂のファイティングポーズ隙だらけ
猫日向蟷螂もいて日を分ける
冬至まで生きてどうする蟷螂よ
蟷螂の冷たき体に夏の夢
12月
何ごとか霜に枯れしは子芋の葉
広島菜あくの強さを日にかざし
雪やんで猫は日差しに毛をなめる
南天の赤だに映えよ雪もよい
どんぐりが机ころころ土恋し
絶頂の時は短し落ち葉散る
たが弛むほどの寒波や湯がしみる
寒大根抜かれし穴から暮れていく
温かき布団抜け出す気合かな
広島菜水の上がらぬ寒波来る
![]()
女郎蜘蛛天に網掛け柿落ち葉
キャベツ食う虫をつぶせば土が泣く
紅葉す空に薄れて昼の月
釣瓶落とし青鷺魚を咥えたる
鮎がけに秋の日優し川の底
独眼の猫に優しき秋の日は
金泉に浸けしタオルの紅葉色(有馬温泉)
買い物の袋を破り秋刀魚の口
秋空を映す河口にボラ跳ねる
奉寄進の幟静に秋日和
月に吼え猫の喧嘩のたわいなさ
白菜とキャベツの安値秋祭り
青虫をつまむ割り箸手に持ちて
小春日や子猫3匹無我夢中
子猫寝し月煌々と夜を照らす
名月や歳の順序に死ぬがよし
落花生臍の緒つけてぶら下がる
秋耕や生死一瞬鍬の先
人と虫と旨さ分け合う落花生
落花生掘れば先客虫の穴
木枯しやくしゃみも遠慮要らぬ場所
熟柿落つ柿の不作や望の月
鍬の刺す柿の落ち葉も色づきし
木枯しや子猫受難の水かぶり
木枯しやガタンゴトントと列車来る
小春日や光が踊る人踊る
秋の影暗さ勝りて日が暮れる
キャベツ食い虫ひたすらに肥る秋
どんぐりを拾うときには子供の目
土に戻してどんぐりが机ころころ
![]()
 ヘラクレス像
ヘラクレス像
ヘラクレスに欅の落ち葉降りかかる
ピカソかと思えば太郎秋日ざし
彫刻に日差し柔らかつわの花
カラス歩く彫刻の森草紅葉
小春日和白大理石人の顔
![]()
茄子の花無農薬にて受粉する
黒蟻のように頑張り甲子園
熊蜂に守られ胡瓜受粉する
添え木越胡瓜の蔓の空摑む
ヒヨの来て瞬きの間に蝉咥え
蜂の飛ぶ長き足はさげしまま
大根十耕猫が土掘る雲の峰
カナカナや母には終の棲家なり
安らかな眠りに引き込む夏蒲団
畑来て腕鼻耳を蚊に刺され
けたたまし音が始まり夕立来
太陽に電気もらって動く蟻
夏去りし風に乗り来る赤とんぼ
花おくらとりて寂しき食べること
大くしゃみしてもススキの穂も揺れぬ
雲の峰ひと夏の無事惜しみけり
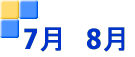
蝸牛殻に人生封じ込め
1.jpg)
羽化終えし揚羽は風の中に住む
羽化終えて揚羽の空は広がりぬ
揚羽羽化色くっきりと羽乾く
羽化終えて飛び立つ揚羽の空広し
子猫の死弔う親子の夜は明けぬ
梅雨晴間壁に張りたる紙増えて
耕せばミミズ虹色日に跳ねて
雷鳴って裏見の滝か通り雨
行く先は角の向くまま蝸牛
蝸牛いずこより来て何処行く
風船に輝く瞳日焼け顔
北海道の青き海より新サンマ
泣くな男の子蝉を取れ
門出でて2度と戻れぬ雲の峰
カマキリの子にて戦う構えあり
燃える日を海が冷やして日が沈む
柿の木のもとで生まれて死ぬる蝉
柿木に子猫3匹蝉を狩る
生きているだけなら虚し蝉の声
陽炎やモンシロチョウの風に浮き
雲の峰背負いて山のたじろがず
夢の中より現に出でて黒揚羽
息するも暑く黒あり帽子なし
せみ時雨原爆の子の塔の鐘
雲の峰原爆ドームの赤レンガ
子猫寝る地べたにごろり露地の風
茄子の花無農薬にて受粉する
黒蟻のように頑張り甲子園
熊蜂に守られ胡瓜受粉する
添え木越え胡瓜の蔓の空摑む
ヒヨ来る瞬きの間に蝉咥え
蜂の飛ぶ長き足下げしまま
大根十耕猫が土掘る鰯雲
カナカナや母には終の棲家なり
安らかな眠りに引き込む夏蒲団
史郎
![]()
牡丹散る花の命の散るごとく
牡丹散る盛り短く時速し
恋の猫皐月の花のもとに伏す
青葉若葉かえで手を出し雨を受け
子猫死ぬそばに親子が添い寝する
青葉風柿の木の猫耳澄ます
それぞれに言い分はある青嵐
子猫ネコすべて育てと親痩せる
雑草も込みの畑や葱坊主
立ち枯れて実らぬそら豆空を向く
霧の中すっと現れ栗の花
白日に晒す肌白し道後の湯
梅雨晴間青きを映し鮎光る
![]()
鯉幟雨に打たれてぶら下がり
桜散る心の窓を開きおり
一夢の短き駅や桜散る
小学生帰ればさみしチューリップ
草抜いて洗い落とせり春の土
ジャガ芽欠きそばに猫来て午睡する
蝸牛親なく子なく妻もなし
蝸牛緑の風の中を這う
霧島の赤色を変え朝な夕な
霧島の花につられて蝶と蜂
五月満開雨の中の蝸牛
![]()
寄り添うているうちが花夕桜
夕日照る桜刻々色を変え
目を閉じて枝垂桜の花の中
絵にならぬ桜の花の雲なりや
御所の桜八坂の桜人の波
花の雲京は桜の多きとこ
加茂川を五条に下る花吹雪
満開の桜に届けブウランコ
住む家が吾の天国侘び助や
菜の花の咲いて楽しい空があり
花びらや桜守するヒヨの声
史郎
![]()
胡蝶蘭冬の寒さを葉に宿し
寒波去る四温の陽気に息を抜き
柔らかき土掘る猫の恋忙(せわ)し
春耕の土に猫来てにおい付け
冬耕の土を春耕ミミズでて
赤き実の心に残る冬ざれて
キュ-と啼き鹿逃げし山雪残る
雪解けの急斜面逃げ親子鹿
晋作の面白うない世の春楽し
震災の1年過ぎて霙降る
なんとまあ柔らかき日よ霜溶かす
天と地の間に遊ぶ春麗
春の日のあたりて溶かすわだかまり
チンチョウゲ花開くとき香を放つ
春霞花粉舞う蝶の舞う
バラの芽の赤く芽吹きて棘とがる
春日和柱建ての音心地よく
春の息吹いっぱい吸って霞む山
それぞれに寝相の違う春の夢
かゆき目の涙の中に白木蓮
バラ色の日々などなくて白木蓮
気合などかけて寝覚めの四月馬鹿
親鸞の意志の強さや白木蓮
白木蓮濁世(じょくせ)の塵を寄せつけず
4月馬鹿猫まっしぐら雌追って
目に涙ぬたの辛子の効き具合
冬の垢流し潤す春の雨
土割ってジャガの芽の出るただ尊(とうと)
葱坊主拳にょきにょき天を打つ
![]()
初夢も見ず早朝の元旦会
元旦の日矢青サギの川渡る
冬耕の土黒々と息をせり
包丁にパシリと割れて寒大根
寒夕焼け烏染まりて塒(ねぐら)へと
寒波来るジンジンしみる湯の温み
格好は二の次マフラー巻きつけて
マスクより下あご動く冬電車
鮟鱇の売られる姿だらしなし
胡蝶蘭冬の寒さを葉に宿し
梅開く四温の陽気に息を抜く
柔らかき土掘る猫の恋せわし
春耕の土に猫来て臭い付け
春耕や光と遊び土と遊び
家建てる杉の木の香の冴え返る
後戻りできぬ齢や冬の川
冬ざれて朝日に光る川流れ
揺すられて身を硬とうする寒海鼠
日の当たるとこから融けて雪の道
白菜もふくら雀も丸くなる
キィーと啼き鹿逃げし山雪残る
![]()
 霜に打たれた芋の葉。
霜に打たれた芋の葉。
・ 冬ざれて猫も獣の顔になり
・ 枯れ菊を刈って手につく香を愛でし
・ 山茶花も覆い隠され雪の花
・ 冬耕の土黒々と風を吸い
・ 海鼠食むいつから日本にクリスマス
・ 海鼠食む寒の硬さを凝縮し
・ 海鼠食む冬至の夜の暗さかな
・ 年賀状まず1枚を書き始め
・ 寒波来る羽毛布団に首を出し
・ 柚子の色黄色増したり寒の雨
・ 白菜の虫も静まる寒さかな
・ 初雪や残りし柿の枝に降る
・ 群雀初雪を飛ぶ野の果てに
・ 芋の葉の霜に打たれて無残やな
・ 大根の葉に霜を置き青々と
川柳
・ 暮れの町パトカー増えて渋滞す
・ サンタさん東北の地に行ったまま
・ 雪だるま日本列島南下する
寒仕込 (西条:賀茂鶴、賀茂泉見学 美酒鍋)
・ 寒の酒仕込みもろみの音を聞く
・ 大吟醸米を削って味の冴え
・ なまじっかなことでは出せぬ酒の味
・ 酒のもと三段仕込手間を掛け
・ 序破急の発酵を経て寒の酒
・ 寒仕込男の戦い始って
・ 酒林倉に香りの新酒かな
・ まんまるに米を精米寒仕込
煌き
・ 芋の露煌き残し落ちにけり
・ 芒の穂残照のなか煌きぬ
・ 日と遊び煌く水面冬の川
・ 花侘びし香り煌く枇杷の花
・ 日の光霜の煌き枯野かな
・ 煌きの時は束の間初日の出
![]()
・ 芋の露(つゆ)光ころがし落ちにけり
・ 干し柿の影を映して障子に日
・ 紅葉(こうよう)も散れば落ち葉の色をして
・ 猫のいる秋日だまりに分け入りし
・ 日だまりを猫と分け合い秋深し
・ 風もなく葉の舞い落ちて霧深し
・ 歌声は心にかよう秋の風
・ 黄葉になりひときわ高き銀杏の樹
・ 付けられたように味付くぶり大根
・ 山紅葉急に進みて子等薄着
・ 猫2匹寄り添って寝る寒の雨
・ 広島菜青臭き香に重し載せ
・ 幸せの猫は冬日に毛をなめて
11月旅行
第1日目備考
11/17 13:00 相生駅改札出口・集合(赤穂へ出発)
(木) (車移動)
日の入り: 13:40 花岳寺駐車場
16:54 14:15 花岳寺400
(車移動)
14:30 歴史博物館駐車場
(徒歩)
15:10 赤穂城跡
(徒歩)
16:10 大石神社420 (写真)
(徒歩)
17:00 歴史博物館200
(車移動)
17:30 赤穂御崎駐車場(柔軟対応します)
18:00 国立公園赤穂御崎
(車移動)
18:30 鹿久居荘・宿泊【水族館料理】12855 (飲み物不含)
兵庫県赤穂市さつき町35-5
TEL:0791-42-1130
第2日目
11/18 8:20 鹿久居荘・出発
(金) (車移動)
日の入り: 9:20 SPring-8駐車場
16:55 11:30 SPring-8(9:30-11:30) (写真)
(車移動)
12:30 たつの・そーめんの里駐車場
昼食1500 (予定)
13:30 たつの
(車移動)
14:00 姫路城駐車場(入館口まで往復徒歩30分)
15:30 姫路城(「天空の白鷺」)(14:00-15:00) 600 (写真)
(車移動)[播但+中国+鳥取自動車道]
18:00 山紫苑・宿泊【かに・フルコース】19970 (飲み物不含)
鳥取市鹿野町今市972-1
TEL:0857-84-2211
第3日目
11/19 8:00 山紫苑・出発
(土) (車移動)
9:15 浦富海岸駐車場
10:30 ジオパーク・浦富海岸遊覧(9:15-9:55) 1200 (写真)
(車移動)
11:30 鳥取駅駐車場
昼食1500 (予定)
12:30 鳥取駅・解散
12:54 鳥取駅発(スーパーはくと
旅行俳句 : 2011.11.17~19
見所の多いい旅行でした
カニを満喫しました
すべて自動車に分乗し、移動しました。
赤穂城址
花岳寺→歴史博物館→赤穂城址→大石神社→歴史博物館
の順に廻りました。
赤穂もあだ討ちの事件がなければ、塩田の町として栄え、
こうも有名になっていなかったと思われます。
兵どもが夢のあと、むなしさが漂ってきます。
運命とはいえ、辛すぎます。
・
落ち葉散る赤穂城址の佇(たたず)まい
赤穂城址ではこじんまりまとまった庭が目につきました。
この庭が幸せであった時のことを語っているようでした。
・
大石長屋落ち葉のなかに石蕗の花
大石長屋は落ち葉の中につわぶきの花が咲いていました。
主人を失い、庭も静かなたたずまいを見せていました。
・
義士石像並んで釣瓶落しかな
大石神社の前に四七士の石像が並んでいて、つるべ落としの
日は暮れようとしていました。
本懐を遂げたとはいえ、無念が伝わってきました。
・
息継ぎの水に釣瓶の日は暮れる
浅野匠の死を知らせる使者が水を飲んだといわれる井戸があり、
使われない釣瓶が夕日を受けていました。
釣瓶落としと、釣瓶をかけてみました。
スプリング8
放射光と呼ばれる光で、原子レベルの微細な構造や働きを観察する
ことのできる最新鋭の装置です。
規模に圧倒されます。一つ間違えば無用の長物となりそうな機械です。
芒が生えている土地に山を取り巻くような形で作られています。
・ スプリング8紅葉(こうよう)の山一回り
・ スプリング8最先端の枯野原
姫路城
姫路城は「天空の白鷺」となり、天守閣の修理の様子が見学できます。
天守閣の大屋根の修理をすぐ近くで見ることができます。
天守閣の瓦をはがし、屋根瓦の葺きなおしを中心に約5年かけて行う
大規模な工事の様子がよく分かります。
・ 秋日差し城の石垣角(かど)尖(とが)る
天守閣が見えず、石垣のみはむき出しで、秋のしざしを受け
光っていました。
松葉蟹
何年か前に来たとき食べた蟹が忘れられず、もう一度来た
ということになります。
何年か前と一緒で蟹を食べることに夢中です。
今度はいつ食べれるか、分りません。もう食べれないかもしれません。
・ 解禁を待って旅行や蟹を食う
・ 一心に一期一会の蟹を食う
浦富海岸
ジオパークの浦冨海岸は時雨れていました。
雨にぬれた岩肌は人の肌のように赤く見えました。
遊覧船でまじかでにい見る島々は日本海の波に洗われ痛々しく見えました。
・ ジオパーク岩肌露骨時雨るるか
・ ジオパーク海鵜時雨れて岩に立つ
史郎
![]()
白木町 井原地区史跡・城跡巡り
・ 稲刈って一段落の幟立つ
・ 尼子氏のゆかりの墓や栗のいが
・ 猪の掘りし土踏んで行く落ち葉道
・ 当たり年小粒な柿の日に映えて
・ さくさくと踏み行く落ち葉匂いあり
・ 日が誘い蛇の出る道柿実る
・ 石組みや夏草枯れてふる月日
・ 秋の七草手にもってあぜの道
史郎
17期会山陰旅行
紅葉愛でバスで向かうは日本海
蒜山や白き薄が出迎える
しぐるるか山陰の日の暮れやすき
しぐるるか欅の紅葉落とすほど
白き波白兎海岸石蕗(つわ)の花
・ 熟柿落ち天下揺るがすこともなし
・ 文化の日朝からテレビオーケストラ
・ 柿の木に追われし猫の実もたわわ
・ 落花生一つのつるに粒一つ
・ 金木犀花ぽろぽろと雨の音
・ 日に映えて過疎化の村に柿たわわ
・ 団扇より大き芋の葉露落とす
・ 意のままにならぬ熟柿の一つ落ち
![]()
・ 舞い下りて一時の夢黒揚羽
・ 鍬もって長靴はいて秋の空
・ 払ってもまた蜘蛛の巣の秋の空
・ 畑打って炎天にミミズ皆跳ねる
・ つる草を意志持って切り夏終わる
・ 悩みなど無いわけがない雲の峰
・ 白壁を白く照らして望の月
・ 柿の葉に空蝉(うつせみ)秋の風に揺れ
・ 蜂の巣の周りをよけて剪定す
・ 西日受け向かい来る蜂身をかわす
・ 女郎蜘蛛囲の中心に身を隠す
・ 夢破れ羽も破れし黒揚羽
・ ボス猫の喧嘩に勝って鰯雲
・ 色づきし柿落ち空の透きとおる
・ 誰が許し得て蜘蛛の囲の掛けられし
・ 白菜を間引くに迷い紋白蝶
![]()
熱中症すでになってる無力感
骸骨になりたいほどの熱さかな
暑さ忘れ感動やまず甲子園
人すらも絡め捕らんとクモの糸
あご出して生きるがやっと暑いなあ
神の意思あるかのごとき甲子園
![]()

畑打つツクツクボウシ鳴き急ぐ
虫の音を聞くにつけても夜の秋
種を蒔くツクツクボウシ蝉時雨
生きていることが嬉しき法師蝉
炎天に足長蜂の羽の音
親に似て善悪は別猫親子
夕立に黒蟻戻る四方より
雷鳴やひとは祭りの熱気冷め
ボランティア会場早々赤とんぼ
うたた寝の夢のつづきの蝉の声
蝸牛ブロック塀に音符書き
蝋燭のくにゃりと曲がり墓参り
油虫叩けど逃げる又叩く
ぶつかって蝉の羽音の暑さかな
秋野菜種まく畑に雨しみて

日に焼けし大地沈めて月の照る
暑いなあ子猫の午睡風吹いて
法師蝉突然鳴いて思い出す
炎天や大根の種蒔きたしや
炎天よりスーパーに入り息をする
浅利取る川の流れや原爆忌
アメンボのやたら多くて川細る
薄き本さらりと読んで夏涼し
涼しそう小泉八雲のの雪女
![]()
青柿や猫の瞳に映る青
1.jpg)
夏草を抜いて作りし風の道
暑いなあ地獄の釜のふた開けて
日割れしたトマトを愛でて持ち帰る

蚊が速しついて行けないもどかしさ
あるものを数えて生きるナスの花
青柿や子猫の育つ取っ組み合い
緑陰に子猫を連れて移りけり
棘の刺すキューリを配る梅雨晴間
夏休み孫の笑顔をお出迎え
孫の来る笑顔が土産夏休み
うすもの(羅)や細き指先透き通る
ぶつかって蝉の鳴き声夜の闇
親に似た子猫の遊ぶ路地の奥
草1本抜かれて蟻の大騒ぎ
しみじみと蝉の声聞く生きている
おす猫の夏のねぐらは無かりけり
![]()
くちなしの白き花散る香と共に
試みに馬鈴薯(じゃがいも)を掘る手に力
失いしものころころと柿の花
偏屈と呼ばれキュウリの曲がりおり
青トカゲ全速力の命かな
やぶ蚊追い梅雨の晴間に馬鈴薯(ジャガ)を掘る
働くは陰日向なき黒ありの
ごろりごろり炎天に馬鈴薯掘る
小雀の掴み損ねて宙ぶらり
梅雨の雨傘の中なる命かな
白き肌のぼり葵は頂に
夏の足女5人のさまざまに
オス猫の尾羽打ち枯れて夏を行く
猫の子の後に続くもままならず
反射した光まぶしき梅雨晴間
短歌
心地よき居場所あること感謝して梅雨の晴れ間にじゃが芋を掘る
試みに堀たるジャガのころころと大きさにまず驚いている
梅雨の雨蛍袋重ければ折れて倒れぬ赤き花なり
![]()
侘び助の白朽ちやすし時早し
オス猫の縄張りめぐり柿の花
日に光る藤の花びら朽ち易し
この春の日差しに生まれ二葉かな
寒に耐え芽を出す不思議力あり
桜散る男の影が踏んでいく
振り返る過去など侘びし紫木蓮
辛夷散る命の終わりであるごとく
侘び助の雨に打たれて頭下げ
満開のさくらを洗う雨の降る
山笑う赤い服着てじょじょ履いて
何ゆえに眉間に皺の花の散る
柿若葉照らす月夜の豊かなる
オス猫のときに争う柿若葉

![]()
3月をめくれば花の満開に
日を受けて淡雪とける芽に光
風の吹く方から冷えて春早し
淡雪の溶けて霞みし山間近
春霞消えぬ間にまず一仕事
光満ち風やや寒き寒戻り
寒戻り木々の芽吹きは萌黄色
萌黄色動かぬ山に春霞
日溜りの花の話が春を呼ぶ
啓蟄や乳飲み子の顔面白し
蓑虫のような子を抱く寒戻り
蓑虫が膝にのっかり子は宝
啓蟄や布団を抜けし人の穴
草燃やす煙霞の中に消え
津波あと雪に非情の情けあり
温み分けよ被災者に降る雪あれど
温み届け被災者に降る雪やまず
菜の花に雪降って大地震
けたたましヒヨの来て鳴く花の園
恋の猫悩みは常に尽きぬもの
相続の話し終わりて梅の花
路地に入りまた路地に入り沈丁花
路地の庭皐月の芽吹き香にむせし
雪解けの水首筋にひんやりと
次郎さん飛びます飛びます天国に
海静かキラキラと冴え返る
水仙枇杷蝋梅香り清し
冬雀日だまり求め動きけり
牡丹雪どかどか降って地に消ゆる
大地震激し鎮魂の牡丹雪
地に消える雪しばらくは降り続く
白魚の赤きはらわた透きとおる
春耕やくさめして鳥威す
春耕の土に寄り来るジョウビタキ
三陸に津波押し寄せ冬星座
余震続く夜を迎えし冬スバル
悲しみが祈りに変り津波見る
嘗め尽くし津波のあとの寒スバル
何ゆえの怒りかなえ(地震)のあとさみし
侘び助や枝に掛かりて朽ちてゆく
刺身にと漫画顔なる鯔売られ
ぼうたんの闇を照らしておりにけり
ぼうたんの照らす月夜でありにけり
じゃが芋の芽を待ちわびている畑
鍬さげて農夫という名春一番

![]()

寒に入る五感鋭くなってきし
寒波来る生身の体熱をもつ
凍てつきし盆地温めて日の光
鴨3羽飛び立つ先の雪の山
大口を空けて鵯(ひよ)鳴く首寒し
広島菜寒を漬け込む樽の底
一期一会分る年代海鼠食う
![]()
〔道後温泉・・何年ぶりかの雪
高速道路一部通行止め〕
道後の湯残りし雪を景色とす
湯煙や残りし雪の白さかな
道後の湯山頂の城残る雪
熱燗や即興踊り悦に入り
ため池や枯野映して伊予の灘
内子歩く障子に影や冬うらら
![]()
深き夜の冴え冴え冷気忍び寄る
遅霜やジャガの芽傷む心痛む
花を愛でイチゴと語りしことやある
大根の穴ぼこぼこと四温かな
蝋梅の香を運び来る東風(ひがしかぜ)
ジャガ芋を植える話題の日が続き
みぞれ降る行き交う顔の様々に
霙降る特別養護老人ホーム
坊様を修行僧に変え寒の雨
草の芽をやさしく濡らし冬の雨

史郎
![]()

雪解けの雨だれごとに日の光
外に出て俳句作れと風花が
天からの贈り物かも畑の雪
厳寒に黒光りする屋根瓦
風花や寄り道をして虫になり
ボス猫の後へは引けぬパトロール
門開けてより寒の空気の入れ換わる
冬物に半額の値の付き始め
手作りの野菜を愛でて寒の内
大寒や野菜にもらう命かな
白菜の甘さ残りて春隣
冬眠の蛙脅かす鍬の先
寒潮に立ち向かうすべなきものを
みぞれ降る鳥も耐えねば生きられぬ
風花や行きつく先は風任せ
風花や地に落ちるまで生きている
枯れ野原キラキラ輝く川の水
寒の入り鳩ヨタヨタと歩きけり
寒に晒す力耕の土黒々と
炊飯器ブツブツブツと雪の降る
露天風呂湯気巻き上げて寒に入る
化石掘るごとくに掘ってヤマト芋
ヤマト芋土の匂いのなかに掘る
早朝の足音を聞く冴えかえる
寒波来る身を硬くする海鼠かな
吹雪くらし鳥帰りゆく塒へと
一羽づつ帰ってゆくか雪の山
天地に光が満ちて雪の山
鍬一撃冬眠の蛙掘り起こす
虫食いの白菜を割るほんのりと
孫と撞く鐘の響きに年明ける

![]()
雪の道足跡残し新年に
寒波来る菜に塩ふって漬けんとす
採りて来て大根おろす甘かりき
初雪や黒き耕土の上に載る
世界の小澤命を削る12月
日溜りを追われし猫の師走かな
落ち葉散る散りし落ち葉は風任せ
尾を立てて怒り心頭恋の猫
ジョウビタキ畑に下りて猫の留守
船長の父が教えし星冴える
鵯(ヒヨ)食みし南天の実の11個
広島菜干せば冬至の日は暮れる
大根下ろしに冬至の海鼠食む
ジョウビタキ一羽きて一羽去る
ジョウビタキいつもの声に振り向けば
山茶花に消えし目白の影を追う
海鼠食むこうまで固き青海鼠
吹雪くらし鳥帰り行く雪の山
![]()
日向ぼこ子猫落ち葉に顔向ける
菜を漬ける庭の山茶花咲き初める
広島菜夜の冷気に水上がる
いずこより枯葉飛びきしベランダに
木偶の坊キャベツ白菜虫の穴
華やかさ過ぎて落ち葉の風まかせ
翡翠の飛ぶ川釣瓶落しかな
昔への記憶の糸や赤のまま
冬鳥を浮かべて流る川暮るる
土瓶蒸し口に残りし茸の香
山口同窓会
唐戸市場トロ箱乾く釣瓶の日
壇ノ浦潮流早し朝の霧
東行の墓訪ねれば石蕗の花
紅葉に日騎兵隊の墓巡り行く
釣瓶落とし暮れゆく光に影長し
干し柿の影が布団に曲かなで
吊るし柿日の温もりを集めおり
女郎蜘蛛網つくろって肥りゆく
つるべ落とし疲れをすべて湯に流し
つるべ落とし子猫3匹遊び好き
子猫3匹視界に納め親の猫
白菜の間隔狭し鰯雲
それも欲これも欲鰯雲
shiro
![]()
鍬の先白く光りて秋耕す
残る夏一雨ごとに消えてゆく
秋冷や物思いする朝の影
水を撒くホース引き回す残暑かな
振り返る人生うたかた雲の峰
こうもりや薮蚊生き生き夜の秋
入道の雲それぞれの顔を持ち
入道の雲が遊びし赤とんぼ
赤とんぼ羽根に赤味をほんのりと
ヒヨやせて炎暑の夏をすごしけり
思惟はるか彼方にかかる鰯雲
大根の種まいたまま芽に出でて
赤とんぼ朝の冷気に下りて来て
夜に目覚め秋の冷気に秋の虫
月こうもり山の幻想夜の秋
陽炎の中を電車が定刻に
人生はうたかたなりし法師ぜみ
縛られて売りに出されしワタリガニ
がぶ飲みすペットボトルの残暑かな
山雲を背負いてどしり残暑かな
木の葉落つ如く舞い下り揚羽来る
炎天を絡めて伸びしつるの草
手のひらが仕事知ってる残暑かな
蜂重く蝶はひらりと宙を舞う
朝影となって寂しき夏帽子
今日もまた入道雲と草を抜く
夏終わる人の生きざま人の顔
死ぬということは結果よ蝉落ちぬ
現れてすぐに消えたる揚羽蝶
耳鳴りのまた始まりぬ夜の秋
うすもののすそ翻す残暑かな
化粧する女の眼残暑かな
携帯を持ってうたた寝残暑かな
うすものの胸のふくらみ残暑かな
早々と半額セール夏終わる
白菜の発芽気になる炎暑かな
稲の香や日照り続きの夏の月
にじむ汗朝から動く積乱雲
骨拾う穢れなき白雲の峰
法名を持って昇天夫のもと
![]()
青き山みなぎる精気雲の峰
白という色は斯くあり雲の峰
白骨を抱きてかえる雲の峰
明け易し蜘蛛は一夜に巣をかける
電線に巣立ちのカラス子は子供
茄子キューリ炎天を生き命がけ
玉の汗薮蚊脅して草を抜く
蝉の声ピタリと止んで思いおり
熱帯夜手の届かないとこ痒し
見取られもせず母逝きし熱帯夜
母逝きしショートステイの明け易し
炎天に命燃え尽き母逝きぬ
失いし母大きなる雲の峰
母の魂昇りて行くか雲の峰
焼き尽す炎天に蝶舞い下りる
平凡な暮らしにニョキリ雲の峰
雲の影落として涼し夏の山
布団干すふかふかの熱帯夜
夏野菜無農薬にて作りきる
日の光集め舞い下り揚羽蝶
![]()
子ツバメの電線に並ぶ巣立ちかな
ゼロ戦のようなすばやさ薮蚊来る
畑の蚊一身に集め草を抜く
梅雨に入る一夜の茸も虫食いに
生も死も天に任せて義母の夏
笑いなく悲しみ多き母の夏
忘れ傘梅雨の最中の駅ベンチ
勢いを持って草抜く梅雨晴間
降る雨は低きに流れ蝸牛
忘られてキューリいっきに肥りだし
一夜にて肥るキューリや母を継ぐ
天に伸ぶ勢い強しキューイ蔓
梅雨の雨まんべんに降る母欝に
骨太に生きる男の大文字
忙しいなどちっぽけな夏の山
雨は嫌やわあ梅雨の雨
野菜作りの道楽にトマト成る
なすトマト天が育てて収穫す
茄子の棘藪蚊の口の尖がりて
ペチュニアの種蒔くに息を止め
薮蚊来る縞繊細に打ちがたし
薮蚊つけ畑より帰る手にキューリ
深入山
![]()
世の中は忙しすぎる葱坊主
まっとうに生きる男の葱坊主
窓開けて風を入れたき五月晴れ
限りある命尊し柿若葉
蟻ふまぬように歩きし柿の花
柔らかく若葉受けとめ雨の音
黒髪を吹き上げ止まぬ青嵐
提灯を吹く風厳し若葉散る
何時からか女郎蜘蛛の子巣を構え
葉も光り鳥も光りて5月かな
鮎釣りや老化の進む近視鏡
五月晴れ派手過ぎる服クラス会
小雀の親離れせぬ棒の先
キューイ棚蜂の羽音の鳴りやまず
蜂の威をかわしてそら豆抜いてゆく
そら豆の1つ子2つ子3つ子かな
炎天に蛍袋蜂を呑み
![]()
青光る虫に命の若葉かな
霧島の重さに垂れる雨上がり
倒れるなそら豆縛り余寒あり
牡丹(ボウタン)の頭重たき空晴れて
葱坊主大根の花畑隅
大根の花に赤味の可憐さよ
葱坊主ミツバチ集め昼寝時
千鳥別尺ヤマザクラ
水温む別尺桜蛙鳴く
田水映す千鳥別尺ヤマザクラ
帰る人来る人別尺ヤマザクラ

皐(さつき)笑むショートステイの母帰る
命燃ゆ霧島つつじ炎(ほむら)立つ
そら豆の芽を止め手に染む香の強し
ナメクジも土地の住人住み分ける
初生りの苺の甘さ虫と分け
初生りのイチゴ天より授かりし
福王寺火渡り
火渡りのほら貝若葉震わせて
ほら貝が春眠覚まし火を渡る
桜
須磨明石同じ嵐に桜散る
桜散る仏頂面をくずしけり
場所取りが桜吹雪の中に寝る
茶わん坂舞妓に花の降りかかる
ただ浮かれただうっとりの桜園
香水に匂い消されて散る桜
ほろ苦き夢もありしか桜花
雨にぬれ雀も桜惜しみけり
日常
薄皮で悲しさ包め葱坊主
人の世に悲しさのあり葱坊主
ジャガ芽摘み開き直って生きてゆく
苗植えてエプリルフールの雨が降る
ケーブルに雨滴連なり四月馬鹿
ケーブルを雨だれ走る四月馬鹿
白き花苺に赤き実を託す
トマト苗ミミズも一緒に埋めてやる
101歳葬儀めでたし桜花
車椅子母に春の陽惜しみなく
種まけば芽の出る不思議母を継ぐ
![]()
春浅き川辺は風の芒(すすき)かな
棒を振り行けば河原の風寒し
河川敷サッカーボールに春の風
安住の暮らしなどなし蓮枯れる
寒もどり苦楽はきたる心より

雨だれの音に目ざめし春の夢
木の匂花の匂や芽吹き時
ため息をついて春日の長さかな
夢破る春の嵐や芽吹きの香
春の嵐みな幻よ人生は
紅茶舞う時は短く春至福

柚子落とす春の嵐を許しけり
黄沙降る甲子園児の頭にも
指先を苺(いちご)の赤に染めて食う
沈丁花虫を集めて春の宴
柚子落とし春の嵐のたわいなさ
桃の花鳥の動きのあわただし
あわただしヒヨの飛び去る花曇り
千代の松猿猴(えんこう)造り芽吹き時

![]()
夜の香や振り向く闇の水仙花
立春やいつもの居場所に居らぬ猫
縄張りを巡る野良猫冬の影

節分の声闇に消え豆の音
冬の鵙畑打つ隙間盗みけり
畑打てば冬の鵙きて尾を振りぬ
風花や暇な人生板に付き
風花や冬の衣の重すぎる
風花や小学生の半ズボン
冬の日は心にやさし屋根光る
身も心もカチンカチンの北斗星
霜柱限界集落炭を焼く
春の日にかざし紅茶の舞うを見る
川面あふれ踊る光や春の音

じゃが芋を植えたと春を告げに来し
玄関に母送り出す陽は春に
突然に春かき乱しヒヨの声
草を抜くミミズは春をかぎ分けし
冬の畑打てば寂しき鵙の来る
畑を打つ人と間を取り冬の鵙
畑打ってミミズを起こす春の風
うたた寝や一駅過ぎて梅の花
桃の花鳥の動きのあわただし
![]()
![]() (晴れていながら風に乗って雪片が舞う状態)
(晴れていながら風に乗って雪片が舞う状態)
風花の舞うて菜漬けの水上がる
風花や桜吹雪と見紛いし
風花やカラスに追われるヒヨの声
風花や天の隙間を抜けてきし
風花や娘の介護手厳しき

新雪に足あと印す今年こそ
ズワイガニ寒きロシアの泡を吹く
みぞれ降る介護の間にも笑え妻
懐に小鳥いだきて山眠る

![]()
年輪をひとつ重ねし寒の酒
初霜や老老介護の身となりし
初霜やそら豆しかと受けとめし
初霜や短き首を縮めたる
初霜や日本に四季のある暮らし

初霜や大根の葉に光たる
霜の猫売られた喧嘩は買いもする
喧嘩して傷なめ世をふる寒の猫
蝋梅の黄葉散りかねて蕾持つ
蝋梅の蕾みの凛と黄葉の中
母娘諍い寒き師走かな
漬ける前の広島菜
蝋梅の朝の光に匂いたる
冴え返るきらきら光る雀まで
初霜や陽だまりによる人雀

暮れの市烏賊の目玉のあっちこち
隔(へだて)てなく降りつむ雪の慈悲心
広島菜雪も漬け込む勢いで
そら豆の雪に潰され耐えるとき
初雪や青虫居場所変えたらん
降れどふれど積もらぬ雪の眠き午後
塩をふりかけ重しを載せる
雪解けるたちまち四方水の音
広島菜巻きを硬くす雪の下
風花や広島菜漬け終わる頃
南天の赤味増したる雪の下

広島菜漬けて重しにまず安堵
食われると知らで海鼠のクリスマス
初雪や小学生の声高き
風花やカラスの羽に積りしや
初雪やデイサービスの迎え来る
初雪や認知の母に笑みのあり
釣鐘に今日の初雪降りかかる
初雪や南天の実の上に積む
![]()
ひとつづつ柿落ちてゆくヒヨの声
青虫をつまんだ手もて飯を食う

打ちたてのかけそばを食うそば祭り
紅葉も山より下り里に散る
吊るし柿寒にさらしてあめ色に
幼子のモミジの手にて紅葉持つ
半纏や幼子の手も散りにけり
絶え間なく苔の緑に降る落ち葉
冬桜咲いて落ち葉は降りやまず
ペット亀ゆっくり歩く12月
小春日や心ときめく川の面
ポケットのどんぐり割れる芽吹きかな
持ち帰る紅葉葉あせてかさかさと
親子でも似てない親子秋時雨
懐かしい二ノ宮金次郎
釣瓶おとし忘年会の友去りぬ
水イカの目の玉ぎょろり暮れの街
日の匂いほしくて布団小春の日
ユリノキの枯葉かさかさ木を離れ
D-51の動輪のもと落ち葉よる

昼の月ハンテン木の落ち葉カサッツ
ユリノキのかさかさかさと落ち葉散る
話し声それともささやき落ち葉散る
かさかさと落ち葉動きてまたもどる
落ち葉散るD-51動輪小学校
引っかかる糸を歯できる暮れの市
発射するロケット(可部小学校グランド)
生きのいい蟹から売れるとしの市
心豊か暮れの買い物茶の香り
![]()
2009
11/5:臼杵
二王座の町なみ散策、臼杵石仏
11/6:竹田、久住
岡城址見学、竹田市内散策、久住高原
11/7:九重夢大つり橋からの紅葉、日田豆田散策
11/5 臼杵石仏



俳句
 身一つで行けばいい旅鰯雲
身一つで行けばいい旅鰯雲
石仏のかなたに湧きし鰯雲
石仏の顔めぐりきて秋日濃し
石仏の優しき顔や石蕗(つわ)の花
二王座を巡れば釣瓶落しかな
河童の絵弥生子の生家石蕗の花
(野上弥生子記念館に芥川龍之介の河童の絵がありました)
石蕗の花 の群生


土居晩翠の「荒城の月」石碑 岡城址の大手門の石組

朝の月列をくずして鳥渡る
岡城址石垣高く鳥渡る
岡城址巡れば紅葉昼の月
紅葉の阿蘇に連なり霧の海
月白く久住連山紅葉す
風誘う久住連山落ち葉かな
九酔渓落ち葉途切れることのなし
九酔渓紅葉下れば日田天領
日田天領町なみ残し秋日ざし
九重夢大吊橋
叶谷史郎
![]()


俳句
団栗(どんぐり)にふと見上げたる秋の空 登りきて手に秋の水冷たさに
奉寄進幟(のぼり)秋日に登山道 池の面人影映す秋の水
走り根を踏んで木漏れ日秋大祭 蟷螂の火渡りの火に向かい行く
金仙の亀福招く秋日和 火渡りの火勢の落ちて般若経
今落ちし漆葉赤く色付きし 焼き尽くす火に数珠かざす秋日和
木漏れ日に般若心経芒の穂 気合かけ火をわたり行く天高し
火渡りやかざす刀に秋西日
叶谷史郎
2009.10.18 福王寺
1.jpg)
1.jpg)
![]()
熟柿(じゅくし)食み終日(ひねもす)聞こえる鵯(ひよ)の声
鰯雲天に網掛け女郎蜘蛛
青虫を付けたまま売るキャベツ苗
青虫を潰しておれば鵯(ひよ)の声
女郎蜘蛛日増しに太り柿熟れる
釣瓶落とし匂いを放つ金木犀
稲雀飛び立って田を巡り行く
秋の水冷たき川を渡りけり
柿抱きて電車にまどろむ至福かな
女郎蜘蛛鳥取る構え天に網
酒まつり
なまこ壁酔いの回りし秋日和
稲刈って昼の酒飲む酒まつり
野菜つくり
広島菜間引きておれば日に疲れ
青虫を掴んで捨てし手を洗う
葬式
経文は分からぬものよ野分去る
頭蓋骨崩れ易しや秋の風
野分去る人の命も白骨に
鰯雲
鰯雲己主張すくもの糸
羽いっぱい広げ鳶舞ううろこ雲
梲(うだつ)ある町並み古び鰯雲
鰯雲ピオーネ蜜柑の値が下がる
鰯雲茜に染まり夕餉の香
山肌にへばり付く家に釣瓶の日
台風の前の静けさ人せわし
黒猫のむくりと起きし秋の雨
化粧する待合室や秋の雨
生きることは難しきかな蜘蛛巣張る
中秋の名月を見に外(と)は明し
熟したる柿終日の鵯(ひよ)の声
棘の刺す秋の胡瓜が貰われて
蝶になることは難し紋黄蝶
青き糞して青虫は太るなり
霧晴れる度に色ずく山紅葉
白と黄と蝶舞う畑に虫殺す
畑より付いてくる蚊を打ち叩く
首筋にひやりと柿の葉落ちて知る
柿の葉が落ちて白菜巻きはじむ
ひとつづつ落ちる音する柿の葉は
静寂の中に柿の葉落ちにけり
トマト胡瓜持ち帰りきて豊かなる
手のひらの胡瓜の棘の新しき
己が場所わきまえて咲く彼岸花
蝶舞って卵一つを産み付けし
真っ裸青山の中露天風呂
雲の峰野良猫蹴飛ばす迫力で
微笑んで子を抱く母に雲の峰
![]()
夏の終わり
夏ばてのため息残す妻の夏
明けやすし目覚めに残る浅き夢
錦帯橋
出番待つ鵜舟の熱気河原風
秋吉台
秋芳洞入り口冷気雲の峰
夏木立抜け来る風の涼気かな
法師蝉忙しく鳴いて移りけり
蜩は山の涼気の中に鳴く
秋芳洞漂う冷気夏休み
櫃田小学校(君田) 今は廃校
廃校のグランドいっぱい星銀河
グランドに芋焼きの火や星銀河
廃校の真っ暗闇や天の川
村人の客をもてなす焼山女
持て成しや項(うなじ)冷たき峡(かい)の道
羅(うすもの)の藍翻し夏終わる
夏終わるダム湖に映る山の青
農作業
草を抜くかえるの居場所残しつつ
カマキリが食物連鎖の中におり
車中より外が涼しき峡(かい)の里
イボガエル殿様ガエル並び出る
叶谷史郎
7月、8月の俳句
梅雨明け
梅雨明けて輝く今日のありそうな
白壁に夏の日当たる目覚めかな
トカゲ去る尻尾(しっぽ)の青さ目に残し
夏木立
抱(いだ)かれて児の目涼しき夏木立
歩くたび児の靴きゅつきゅ夏木立
原爆忌
原爆忌語り部の地獄色あせず
畑にクワ忘れっぱなしの原爆忌
虫
黒揚羽夢の如しや柚子の木に
ジグザグに歩いて蟻は急ぎ足
農作業
つる引けばカボチャつき来る2個3個
炎天に蚊もなりひそめ草を抜く
炎天ににわか百姓玉の汗
富士山の飛魚でいてありがとう
雲の峰
夢が消え夢が生まれる雲の峰
空に住むトンボ見上げて雲の峰
草に住む虫の多さや雲の峰
雲の峰俺の出番となりにけり
覇を競い空に広がる雲の峰
歯が抜けるふつふつと湧く雲の峰
叶谷史郎
5、6、7月 俳句
梅雨、夏、野菜作り
迫力を持って草抜く梅雨晴間
梅雨晴間洗濯乾く白さかな
朝2発夏祭の花火鳴りしのみ
ばりばりと草の根を掘る茄子の花
鵯夫婦来てくわえたる蔓長し
あるがまま対峙して見る夏の山
畑より薮蚊つき来る梅雨曇
梅雨の月ショートステイの母見しか
赤とんぼ下り来て薮蚊影ひそめ
青き山ただひたすらに霧上る
柿の花ぽたぽた落ちて服乾く
新物の秋刀魚氷に目が黒き
どくだみの花満開の母の庭
虫つけて持ち帰りたる茄子キューリ
空に伸びキューイの蔓は空つかむ
かまきりの子の構えたる太極拳 (草抜きにかまきりの子が出てきて、戦う姿勢)
山芋の芽は植えただけ出でにけり (当たり前のことが、当たり前におこる)
寝る起きるカサブランカの香の中に
開く窓は開け放したる梅雨晴間
雨霧の山駆け上る夏は来ぬ
梅雨の雲低く流れて山隠す
栗の花出雲八重垣露天風呂 (奥出雲)
栗の花天の真井の焼鳥屋 (奥出雲に行く途中、天の真井という名水あり)
炎天に飛び出してゆく若さかな
雨に濡れ蛍袋花重し
鶯の遠音抗う妻と母
認知症子の顔になる母の夏
茄子のとげ刺されて朝の目覚めかな
表見せ裏見せ鳶の青嵐
動かざるものに山あり青嵐
紫陽花の雨を含みて色匂う
黒南風や雨を待ちたる鮎の川
叶谷史郎
オホーツク流氷クルーズと感動の北海道4日間
第1日目3/6 釧路湿原と阿寒湖
いつかオホーツクの流氷を見たいと思っていました。格安のツアーがあったので奥さんと一緒に行くことにしました。
3月6日~3月9日の3泊4日のツアーに参加しました。
第1日目は広島空港を9:10に出て、釧路空港に15:20に到着し、バスで釧路湿原を見ながら、丹頂鶴の
越冬地鶴居村に行きました。絶滅の危機を脱して、現在丹頂鶴は1,000羽くらいにまで増えているそうです。
今は鶴にとっては恋の季節で、時々華麗な求愛ダンスが見られました。
16:30今日の宿泊地、阿寒湖畔の阿寒ロイヤルホテル到着となりました。
 釧路空港
釧路空港
釧路空港には予定どうり15:30ころに到着しました。天候はあまりよくなく、雨が降ったり、やんだりの天候でした。
バスガイドさんによるとこの時期に雨が降るのは大変珍しいのだそうです。この後、雨は霙に変わり、雪になり
ホテルに着く頃には吹雪になっていました。夜は雪を巻き上げる地吹雪となりました。
結局この日予定されていた阿寒湖氷上フェスティバル「冬華火(ふゆはなび)」は中止ということになりました。
阿寒湖の氷は厚く張っていて、雪かきのトレーラーが載ってもびくともしません。
夜は窓の外の地吹雪を眺めながら、これが北海道だと感心したり、感動していました。
勿論窓は2重窓になっていました。2重窓でないとダメというのがよくわかります。
バスガイドさんは完全などさん子で、ぽっちゃりとして、寒さには強そうな人でした。
会話に魅力があり、何でもよく勉強し、頼もしそうな人でした。美貌とスタイルの点では昼間見てきたJALの
スチュアーデスさんには劣るのですが、会話では超一流です。
私は北海道に来るたびにバスガイドさんの話術にはいつも感心しています。何時間もバスに乗っていても乗客を
飽きささず、次から次にと面白い話が出てきます。
少し褒めすぎかもわかりませんが、綾小路キミ麻呂の話術を聞いているような気がします。
それでいて、名所、旧跡の説明はきっちりとしています。
ノートを見るわけでもなく、アドリブで次から次にと話が進んでゆきます。このプロ意識にいつも感心させられます。
スチュワーデスさんと比べて、バスガイドさんの方が難しく、頭も体力もいるような気がします。
この点ではスチュワーデスさんもバスガイドさんを見習う必要があります。
 トメさんの給餌場
トメさんの給餌場
釧路湿原は面積が2万6000h(ヘクタール)あり、冬場の丹頂鶴の越冬地となっています。
その他貴重な動植物が生息しています。
最近、温暖化の影響からか、段々と釧路湿原が乾燥してきてるそうです。
丹頂鶴が絶滅しかかったとき、阿寒中学鶴クラブ、トメさんの活躍、地元の人の温かさが鶴を絶滅から救ったそうです。
鶴にとっては冬の餌の無い時期が最も厳しく、給餌場で餌を与えているのだそうです。
鶴は世界に14種類生息し、日本には6種類が来ています。
丹頂は釧路湿原が住みかで、羽を広げると2mくらいあります。大人になるまで4年かかります。阿寒町に
国際鶴センターがあります。丹頂鶴は貴重な自然からの贈り物なのです。
北海道の原住民はアイヌです。地名に難しい読み方のところがたくさんあります。
アイヌの言葉を漢字にしたものがたくさん残っています。
「カムイ ポプニカ アーホイヨ」は「神様どうか願いをかなえてください」ということだそうです。
寝る前に3回唱えれば願いがかなうそうです。
北海道の三大珍味は①エゾ鹿 ②トド③熊 の肉だそうです。
北海道では馬の肉は食べません。?
北海道ではスタッドレタイヤを冬タイヤ、一般タイヤを夏タイヤといっています。
また鹿と車が衝突する事故が起こります。そのために鹿保険があるそうです。
俳句
・ 丹頂の声の響きて雪に消え
・ 丹頂の求愛ダンスふわり浮き
・ 夫婦岳丹頂ふわり雪に下り
・ 丹頂の棲みか湿原雪の原
・ 風のみの釧路湿原冬ざれる
・ 果てしなき釧路湿原もがり笛
・ 北海道梅より先に桜咲き
・ 避けられぬ春来る前に天気荒れ
・ 滑り止めが商売になる鶴居村
・ 丹頂は見えず湿原もがり笛
3/6釧路空港を出て、3/9千歳空港までのバスの通路
 4/6と書いてあるが3/6の間違い
4/6と書いてあるが3/6の間違い
第二日目は摩周湖ー硫黄山ーオシンコシンの滝ー知床ウトロ温泉
第三日目は網走の流氷ートーフツ湖の白鳥ー銀河流星の滝ー層雲峡温泉
第四日目はアイスパビリオンーノーザンホースパークー千歳までのバスの旅
と連載します。
第2日目 3/7 阿寒湖から摩周湖に行き、知床のウトロ温泉までのバス旅行です
今日の出発はAM9:30で意外に遅い出発となっています。
昨夜は地吹雪でどこにもゆけませんでしたし、「冬華火」は中止になりましたので、比較的早く眠りました。
朝は6時頃目が覚め、食事は7:00頃食べ、出発までに2時間くらい時間があります。
阿寒ロイヤルホテルから、阿寒湖は見えていましたので、歩いて行ってみることにしました。
今日は昨夜の低気圧も去り、朝からいい天気で、まぶしいばかりです。
昨夜の雪が積もっていて、一面の銀世界です。昨夜雪が降らなくてもこの時期の北海道はいつも銀世界です。
マフラーをして、厚いダウンののジャンバーを着て完全防備で出かけました。
やはり外は寒く、顔がピリピリします。こんな寒さは初めてです。
北海道に来て第1番注意することは、転ばないようにすることです。バスの中で搭乗員さんが4日のレンタルで
500円の滑り止めの商売をしていました。
私は馬鹿にして、滑り止めなどいらない、と思って、レンタルしませんでした。
それとつけたり外したりがめんどくさいのです。うちの奥さんはレンタルしていました。
除雪車が2台道に積もった雪を除雪しています。除雪は北海道の大事な仕事だそうです。
通りでは除雪車が人間よりえらそうに除雪作業をしています。滑らないように、ペンギンのようにヨチヨチ
歩きです。
阿寒湖の氷の上のイベント会場


阿寒湖の雪像


阿寒ロイヤルホテル
阿寒湖は氷で覆われ、その上に積もった雪でとても湖とは思えません。
その氷の上で除雪車が作業していました。氷が割れるということは考えていないようです。
私はこんな大きな湖が凍ってしまうなんて、想像すらできません。
この上でイベントが行われ、雪の建物、かまくらに似た様なものも建っています。
中国からの観光客が北海道に雪を見にやってきているようです。
確かに北海道では団体で来ている人が中国語のような言葉を話しています。
・ 氷上にかまくら建てて蔵立てて
・ 阿寒湖の氷の上の人の道
・ 人よりも除雪車威張る雪の道
バスガイドさん添乗員様おはようございます。
阿寒湖を後にして、バスは摩周湖に向かう。霧が出ていませんように。カムイポプニカアーホイヨ。
途中で寄る道の駅のソフトクリーム、芋団子はおいしいとバスガイドさん言っています。
バスガイドさんがおいしいというと、乗客は半分くらい芋団子、ソフトクリームを買ってしまいます。
北海道で芋というとジャガ芋です。芋焼酎というと、ジャガ芋かな? ジャガ芋の焼酎は売っていました。
そのほか網走の脱獄饅頭、養殖のマリモなど売っているそうです。
重大発表。昨日の雪で、摩周湖に行く道が通行止めだそうです。回り道をして、昨日見学した鶴居村を通る
道を行くとのことでした。
冬の北海道は通行止めとか,船の欠航とか、雪とか霧で飛行機が着陸できないことなどしょっちゅうだそうです。
このバスにかんしては、そのつど、ドライバー、ガイド、搭乗員が対策会議を開き、どうするかを決めているということです。
釧路湿原はラムサール条約認定第一号となったそうです。
この湿原は釧路川からの土砂により乾燥化が進んできています。貴重な北山椒魚、トンボなど生息しているそうです。
トメさんの給餌場が見えてきました。丹頂が3羽雪の上に休んでいます。丹頂は雪の上でも良く似合います。
「サルルンカムイ」湿原の神様という意味だそうです。鶴が湿原の神様かどうかは聞き漏らしました。
鶴は1000年といわれていますが、82歳まで生きた鶴が最高記録だそうです。
バスは弟子屈町に入ってきました。テシカガ町と読みます。摩周プラザ出少し早い昼食となりました。
ここではシシャモ、半かわきの氷下魚(コマイ)がおいしいそうです。くさやと同じで少しくさいそうです。
サンプルを食べるもよし、おいしかったら買うもよしです。
雄阿寒岳、雌阿寒岳が白く光っています。二つあわせて夫婦岳といいます。
・ 丹頂の声湿原に冴え渡る
・ トメさんの給餌の村の鶴の声
・ 雪原を流るる川に春の音
・ 半乾き氷下魚をあぶる昼の飯
摩周湖は「カムイトウ」といわれ、神の住む魔の湖という意味だそうです。周囲24k、水深210m。
透明度が41.6mでバイカル湖と同じくらいです。
この湖でもう一つ不思議なことは水の入り口と出口がはっきりしていないと言うことだそうです。
しかも水位はいつも同じということです。霧がかかればますます神秘的ということになります。
私は摩周湖に3度くらい来ましたが、いつも晴れていて神秘的な湖は見ていません。いつも中にある島を見ています。
この湖はほとんど凍りません。でも突然凍ってしまうことがあるそうです。
摩周湖は高いところにあって、眼下には根釧原野が広がっています。山には白樺がきれいな木肌を見せています。
根釧(こんせん)原野は釧路湿原も含んだ原野ということになります。全部まとめて釧路湿原国立公園になっているようです。
根釧原野にはムツゴロウ王国があり、ムツゴロウさんも帰ってきているとか?
懐かしい「君の名」に出る美幌峠を通れば屈斜路湖に行けます。
・ はるかなる根釧原野冴え渡る
・ カムイトウ島見せ雪の西別岳 (摩周湖の島が見える。近くにシベツ岳が光っている)
・ 白樺をぬけて斜里岳見え隠れ (雪の積もった斜里岳の姿は見ていて飽きない)
硫黄山によりました。木の生えていない山で、ところどころから蒸気が噴出し、きつく噴出しているところは
黄色になっています。箱根の大涌谷に良く似ています。
亜硫酸ガスの臭いか、硫化水素のようないやな臭いは少ないようです。
地熱の影響で雪は溶けています。山全体が地熱で雪がないのかというと、そうでもありません。
煙が出ていないところには雪が積もっていますが、周りに比べれば雪は少ないようです。
蒸気が噴出している方の地面は雪が全然積もっていません。暖かいんだなというのがわかります。
マグマが地表近くに来ていて、活動が盛んなのだと思います。
私はこのあたりは手帳に何もメモしていません。うつらうつら気持ちよく昼寝でもしていたのかもしれません。
昼飯でも食べて、バスにゆられているとすぐに眠くなってきます。バスガイドさんによるとバスの振動は羊水の
中にいる子供の受ける振動に良く似ているんだそうです。だから眠くなるのだそうです。
しばらくゆくと海岸線に出てきました。網走湾です。はるか彼方はオホーツク海です。
バスガイドさんが「海岸線に流氷が見えます」といっています。私はバスの海側に座っていたのですぐに海岸線を
見ました。流氷が見えます。少し沖には大きな流氷、海岸線には小さな流氷が打ち上げられ、海の上に浮いている
流氷も見えます。テレビでは見たけど、実際の流氷を見るのは初めてです。
今年は流氷の来るのも遅く、去るのも早いのかなということです。
流氷は北風が吹くと海岸線に近づき、南風が吹くと海岸線からはなれて行くそうです。
まだ諦めることはありません。北風が吹くと流氷は現れますよと、バスガイドさんの力強い言葉に励まされ
明日のオーロラ号に期待します。
流氷がくると、大鷲、尾白鷲が来ます。もうきているので海岸線の木の枝に注意してみていてください。
尾白鷲は体が茶色で尾が白、大鷲は黒っぽくて尾が白いそうです。
かもめがたくさんいます。かもめの足はピンク、ウミネコの足は黄色だそです。
あれが尾白鷲か。あれはトンビです。
バスの中からではなかなか尾白鷲も大鷲も見つかりません。
オシンコシンの滝に着きました。双美の滝として知られる知床八景の一つだそうです。
オシンコシンというのはエゾ松が群生するところという意味だそうです。
滝を見に行く道が坂道で、雪が積もり踏み固めてあるので、いつ滑って転んでもおかしくありません。
オシンコシンの滝を後にし、今日の宿泊地の知床ウトロ(宇登呂)温泉です。お宿は知床プリンスホテルです。
ウトロとは岩の間の細道を通るという意味だそうです。羅臼連山羅臼岳も奇麗に見えています。
食事が終って、ウトロ港でオーロラファンタジーがありました。
知床でオーロラを見たという言い伝えがあり、地元の人がオーロラを再現しょうとするイベントです。
地元の人が協力して、知床を盛り上げようという意気込みが感じられました。
温泉に入って見に行くと風邪を引くので、温泉にも入らず夜空に繰り広ろげられる光のファンタジーを見ていました。
・ 大鷲や流氷の風襟を立て
・ カメ島に流氷寄せて舞うかもめ
・ ウトロの湯流氷の去る南風
・ 流氷やオシンコシンに南風
・ 流氷やアムール川より長き旅
・ クリオネは赤き光のホタルかな
 海岸に打ち寄せられた流氷
海岸に打ち寄せられた流氷
知床から網走までの海岸線で流氷が見られた

知床オーロラファンタジー
オーロラファンタジーが終って、帰り道夜空がよく見えました。
大熊座がみえたので、北斗七星はないかと探し、諦めかけたとき北斗七星が見つかりました。
柄杓の延長線上に北斗星が輝いていました。妙に安心した気持ちになりました。
・ 北斗星柄杓の水の凍てつきぬ
3日目 3/8 流氷砕氷船「オーロラ号」クルーズと層雲峡
旅行中の食事は朝と夕食はホテルで出たものを食べることになります。昼の食事はオプションで自分の好きなものを
メニューの中より注文します。
夕食はかなり豪勢なものが出て、全部食べるとどうしても食べ過ぎになります。朝はたいがいバイキングのようなもので、
これもおいしそうなものが出ていて、ついつい食べ過ぎになってしまいます。
またバスの中ではバスガイドさんがおいしいといえば、アイスクリーム、芋団子、チョコレートなど食べてしまいます。
運動不足と食べすぎで、北海道では1k~2kくらい太るのではないかと思います。
また旅行が終ればもとの体重に戻るでしょう。
昨日の知床プリンスホテルの夕食は量も多く、味も良かったと思います。食事を楽しむのも旅行の楽しみです。
バスガイドさんも言われていましたが、北海道の米は硬くて、味も本州にくらべよくありません。
これは朝、食事をする時にわかります。温かいご飯に味噌汁、海苔がついても米がおいしくないので何か物足りません。
北海道に来て花粉症がよくなりました。まだ花粉が飛んでないと思っていましたが、北海道は杉の木がないそうです。?
針葉樹ではエゾ松、とど松よく知られています。白樺は花粉を飛ばすそうです。
花粉症でも全ての花粉がダメなのではなく、私の場合はスギ花粉に限定されています。ヒノキの花粉になると、
ほとんど花粉症の症状は出ません。
今日の天候は晴れです。バスガイドさんから残念な情報が入りました。
オーロラ号は風と波のうねりがきついので、欠航となりますということです。その代わりに、天都山展望台と流氷館のほうに
案内しますということになりました。
対策本部でそのように決まったものと思われます。安全を考えての欠航は仕方ありません。
海岸に寄せてきている流氷を見ただけでも私は満足しています。たとえ船に乗れてとしても流氷のあるところまで
行けるかどうかははわかりません。オーロラ号の料金、2000円くらいが払い戻しになりました。
流氷は40~50km先くらいにあり、オーロラ号でゆけるのはせいぜい10kmくらいまでで、流氷があるところまで
ゆけるかどうかわかりませんということでした。
冷たい北風が吹くとオホーツク海は荒れます。オホーツク海の流氷が沖に見えるのは、2月初め頃です。
水平線に白く見えて、北風とともに流氷は海岸に寄せてきます。今年は流氷が見えるのが遅かったそうです。
温暖化の影響が出ているのでしょうか。
海別岳(うなべつだけ)、斜里岳(シャリ岳)が白くきれいに日に光ってみえます。
北海道の道路は直線道路が多いいとゆうことです。
前がかすんで見えなくなるほど見事に道路がまっすぐに引かれているところがあります。
まっすぐな道路がどこまでも続いています。運転手さんは眠くならないのでしょうか。
雪が溶けて、青い草のようなものが出ているところが所々見えます。秋まき小麦だそうです。
北海道では麦踏みは雪がしてくれるので、しなくてもいいそうです。
これだけ広い畑の麦踏をすれば大変です。もう少しすると、ジャガ芋、玉ねぎ、アスパラ、ビートなどを植えられるそうです。
ビートは甜菜です。葉は大根に似ていて、カブの部分が砂糖になります。グラニュー糖です。
この時期雪がとけ、地肌が見えるのは珍しいそうです。
 トーフツ湖白鳥公園
トーフツ湖白鳥公園
トーフツ湖は周囲26kmの水深3mくらいの湖で、白鳥はアマモをたべています。観光客がいるときは、白鳥の餌として、
食パンの耳が売られていますので、白鳥は餌をもらって食べています。一袋100円です。
鴨も白鳥以上にいて、取り合いながら餌のパンを食べています。
近くの畑でも餌を食べるそうです。春になると白鳥は帰ってゆきますが、ダイエットに失敗した白鳥は帰らずに
残っているそうです。白鳥の世界も人間以上に厳しいんです。
北海道の小学校はスケートリンクを作ります。冬のスポーツとしてスケートをします。昔はスピードスケートをしていましたが、
今は、フィギャスケート専用となっています。スピードスケートを教える先生がいなくなったのだそうです。
浜小清水には小清水原生花園があり、黒百合、エゾヒツゲ、はまなすがあります。この時期は原生花園はクローズしています。
流氷船に乗る予定の網走港、網走駅を見て、流氷館と展望台に向かいました。
・ 欠航の港に探す尾白鷲
・ 縦書きの網走駅や雪の中
バスガイドさんはあれは大鷲だといっていましたが、私にはトンビにしか見えませんでした。
ここらにいつもいるという所に尾白鷲はおらず、見えるのはカラスとかもめばかりでした。
流氷館は大きな流氷が展示してありましたが、まだ小さい方だそうです。
流氷は直接触ることもでき、この部屋の温度はマイナス18度で、ぬれたタオルをまわすと、ピンと凍ります。
しばれ体験は北海道では夜中に外にでるといつも体験することができます。
映像で流氷が押し寄せる様子、流氷とともにやってくる動物なども映し出されていました。
ここで初めて尾白鷲の飛んでいるのを見ました。
クリオネ、フウセン魚、ナメダンゴの水槽もありました。
天都山展望台からはオホーツク海、網走市街、網走湖、能取湖そして知床連山が見ることができました。
網走海鮮市場で食事をして、網走ともお別れです。
網走の永専寺の山門は古い網走刑務所正門を貰ってきて門としているということです。明治村が欲しいといった
そうですが断ったということです。バスの中からチラット見たのですが由緒ありそうな門でした。
網走から層雲峡まではかなりの距離があり、3時間くらいかかります。
食事を終った後で、温度も丁度よく、バスに揺られていると居眠りしてしまいます。
途中、北海道野生王国により、キタキツネの放し飼いを見ることになっています。
北海道のお土産はあるものが急に人気が上がり、売り切れの状態になります。
それだけ観光客が多いいということでしょうか。
網走には脱獄饅頭があり、新しいのが出所饅頭だそうです。
今一番人気があるのが生キャラメルだそうです。一部の生キャラメルは売り切れが続いています。
生チョコも人気があります。白い恋人は一時発売停止になりましたが、今は売られていました。
北菓楼の甘エビの開拓オカキも午前中で売り切れるということでた。行ってみたらありませんでした。
孫にお土産なにがいいかと聞くと、「マリモッコリ」のキーホルダといっていました。
マリモッコリというのは「まりもの人形」がキーホルダーについているようなもので、子供に人気があるものです。
野生の王国「きつね村」に到着です。ムツゴロウさんの野生の王国とはちがいます。
放し飼いといっても雪が積もった野原に柵がしてあるようなところです。
雪が深くて近づくことはできません。きつねも見えません。
雪が積もっているので、きつねは隠れているのだそうです。檻の中にきつねが5,6匹いました。
冬毛でよく太ったかわいいきつねですが、人を見て警戒していました。少しダイエットに失敗しています。
・ 北キツネ村とは言えど雪の中
・ 檻の中冬毛のキツネ丸くなる
北見の方は畑作が中心で、赤花豆、白花豆、ハッカが取れる。ハッカ成金も出ました。
ハッカは肩こり、おへその周りにつけると便秘、こめかみにつけると頭痛に効くといわれます。玄関、風呂に一滴
おとすといい香りがします。エジプトの王妃の棺の中にハッカが入っていたといわれています。
石北峠を通ります。この峠は今日のAM11:00まで通行止めでした。除雪が終って今は開通しています。
標高1050mの峠道を越えてゆきます。
銀河、流星の滝に来ました。銀河の滝も流星の滝も凍っています。凍滝(いてたき)です。完全には凍っておらず、水が
窓のようなところから少しだけ下に落ちているのが見えます。
滝がこのように凍っているのは始めて見ました。イテタキというのを広辞苑で引いてもでてきません。
俳句歳時記にはでていました。凍雲、凍鯉、凍蝶、凍土、凍鶴、凍星、凍蜂などあります。凍を全てイテと読みます。
七星の柄杓が落とす冬の滝 有馬朗人
というくがのっていました。こんな俳句が作りたいと思います。
凍滝はよく写真では見ることがありますが、実際に見るのは初めてです。氷点下の世界でなくてはこういうのは見れません。
昨日の夜降ったのか、さらさらの雪が積もっていました。さらさらの雪は雪のた玉できないということだったので、
雪の玉を作ってみました。確かに雪の玉はできにくいし、できてもすぐにこわれてしまいます。
・ 凍て滝の銀河流星細る水
・ 凍て滝の命つなぎて水の落つ
・ 握れども玉にできない粉の雪
・ さらさらの雪にはできない雪だるま
夜のイベントとして氷瀑祭があることになっています。氷点下6度~10度くらいはこの辺りでは珍しくありません。
川の水を吹きかけて凍らせ、建物を作って、光りをあて幻想的な世界を作っています。
準備は12月頃から、石狩川の水を使って行われるそうです。
昼間見るのと、夜見るのでは少し感じが違います。
こんな大きな建物をよく作ったなと感心させられます。
建物の内部は、トンネルのようになっていて、人がすれ違えます。階段があって二階にも上がれ、
窓から外の景色がみえます。


氷幕瀑祭の会場 夕方 流星の滝


氷爆祭の会場 夜
夜の氷瀑祭の会場は寒く、完全武装していても体が冷えてきます。
足元も滑りやすくなっているし、早めに退散することにしました。
4日目: 層雲峡を後に千歳までバスの旅
今日は上川のアイスパビリオンを見て、味覚のバザールで昼食、ノーザンホースパークを見て、新千歳空港から
羽田にゆき、広島空港には21:00着となります。
旅行の最終日となりました。3日目が疲れていたような気がしますが、ようやく北海道の寒さにも慣れてて来たようです。
部屋の中、バスの中は暖かいので外にでる時だけ気をつければ寒さも気になりません。
旅行中一度も転びませんでしたといいたいところですが、一度転びました。横断歩道を渡ろうとした時です。
踏み固められた雪の上に乗ったときです。お尻に付いた雪を払って辺りを見たら、夕方だったので人はあまり見ていませんでした。
今日の最高温度は6℃だそうです。この時期ではめづらしく、一気に雪解けも進むのではないかということでした。
石狩川、黒岳の山並みが見えています。石狩川は流れ流れて169km。アイヌ語でイッシュカリ別といい、屈曲の多い川という意味
だそうです。別は川をいうそうです。
層雲峡ののそそり立つような岩肌は柱状節理という岩です。大雪山は横臥柱状節理でできているそうです。?
大雪山は北海道のほぼ真ん中に位置し、大雪山をはじめ、黒岳連峰、旭岳,十勝岳連峰などのいろいろな山が集まっています。
その中で旭岳が一番高い山です。今の北海道の山は純白で日に輝いている姿は本当にきれいです。
上川のアイスパビリオンではダイヤモンドダストが見れるそうです。寒いときに空気中の水蒸気が凍り、太陽の光りで
キラキラ光るのをいうそうです。
そのほかマイナス41℃の体感体験ができということでした。
実際にアイスパビリオンではダイヤモンドダストを見ることができました。ほこりが日に光っているように見えますが、
氷ですからガラスの粉を空中に撒いたように見えました。
低温体験ではマイナス20℃の部屋で、さらにつめたい風を発生させ、マイナス41℃を体験できるようになっていました。
体が寒さに慣れているのと、しっかり着込んでいましたのでさほど寒いとは感じませんでした。
中にいた時間もせいぜい10分程度でした。低温室を出ると、温かいきのこ汁のサービスがありました。
外にでると「なんチャってボブスレー」というのをやっていました。雪道をソリに乗って、5人くらいが数珠つなぎになって
滑っていく遊びです。子供の遊びのようですが、大人も興奮するということです。
実際に滑ってみると、かなりのスピードが出るのと、コーナーを回るときそりが浮いて、壁面を滑るような状態になります。
大人も興奮するという意味がわかりました。


バスガイドさんはさかんに面白い話をしていますが、昼飯を食べたあとは眠たくなってきます。子守唄です。
旭川を通過する時に、旭山動物園の話をしていました。
冬の動物園は白熊が元気です。旭山動物園の入場者は日本一だそうです。
有名なのがペンギンの散歩だそうです。雪の上をペンギンが並んで歩いているのを見たミニスカートの女の子が
ペンギンは寒くないのですかと質問したそうです。
そうすると、逆にあなたは寒くないのですかと聞かれたそうです。
釧路動物園の白熊君はオスだと思っていたのにメスだったそうです。白熊は間違われてどう思ったのでしょうか。
日本で一番広い動物園は釧路動物園です。
動物の食事をしているのを見てもらいます。もぐもぐタイムが旭山動物園。パクパクタイムが釧路動物園です。
北海道のお米はまだまだです。キララは粘りがすっくなく、おぼろ月はすごく粘りがあります。
旭山動物園でお米を売っているそうです。国の政策で北海道ではお米の生産は制限されています。
スイカつくり、メロンつくりが行われています。デンスケスイカは真っ黒でおいしいスイカです。
夕張メロンは5月、6月に初せりが行われ、景気が悪いと値段が上がるそうです。
美唄ー岩見沢ー江別ー恵庭ー千歳とバスは進んできました。
札幌はサツポロ別で乾いた大き川の意味だそうです。
札幌は屋根に積もった雪が落ちて人が埋もれてしまう。雪下ろしをしていた時に落ちる。
それを防止するため、どことなく箱のような建て方をしている。屋根から出る煙突がなくなり、
FF式の方法に変わってきている。
玄関は2重になっている。
総理大臣専用機は千歳空港においてある。千歳空港は乗客数日本一の空港である。
新千歳空港のお土産売り場でお土産を買って帰ってきました。ここのお土産売り場には北海道のお土産は
ほとんどなんでも売っていました。
冬の北海道もなかなかのものでした。
これは2006.11に北海道3泊4日で北海道に行ったときの俳句です。
叶谷史郎
生活ほっとモーニング2月16日放送
「夢の3シェフ競演」これだけで幸せ!冬の感動スープ
を見ていました。
日本料理、イタリアン、中国料理を代表する3人のシェフが競演する月1度の人気企画となっています。
私も時々この番組を見て面白いなと思っていました。
今日も見ながらやはり面白いなと思って見ました。中島さん、落合さん、孫さんは日本料理、イタリアン、中国料理の
代表だけあって、料理に絶対の自信を持っていて、ブレが感じられません。
それで好奇心も旺盛で、自分の得意とする料理との比較で感想を言われています。それを面白いと感じます。
今日の最初はイタリアン・落合務さんの「冬野菜のズッパ」です。
ズッパとは、イタリア料理で「スープ」のこと。野菜たっぷりの、まさに「食べるスープ」です。
余分な調味料やブイヨンを使わず、野菜のうまみを引き出します。ペーストにインゲン豆を加えることで、
口当たりが良くなり、コクとうまみがいっそう増します。
次は中華料理・孫成順さんの「大根と金目鯛の白湯(パイタン)」です。白くてとろみのあるスープ、白湯(パイタン)。
本来は、豚骨や鶏がらを長時間煮込んで作る、手間のかかるものですが、今回紹介していただいたのは、孫さんの
お母さんが家庭で作ってくれた思い出の味です。短時間でできました。
最後は日本料理・中島貞治さんの「魯山人風 沢煮椀(わん)」です。
中嶋さんが祖父・父から受け継いだ伝統の一わんです。にんじん・しいたけ・ささがきごぼうなど、食感も色もさまざまな
7種類の具と、香り高い出汁の組み合わせ。豚の背脂が、食べるころにわんの中で溶けて、絶妙なコクを出してくれます。
私はこの3人はすばらしい料理人だと思っています。まず3人の競演でテレビに出たこと、料理を作る時、惜しみなく
手の内を見せていることです。途中で味見をさせ、味の変化を見てもらっています。
自信がなければこれはできません。ポイント、ポイントでなぜこうするかを説明してゆきます。
何れも料理のプロですから、ごまかしがききません。こういう場合、イタリアンではこうで、中華ではこうで、日本料理では
このようなテクニックを使うということが3人の話からよくわかります。
できた料理を食べながら、少年のように興奮し、味に対しての飽くなき探究心がうかがわれます。
お世辞で「ああおいしい」というのと違う味わいがあります。
3シェフの競演によって、お互いが刺激し合い、創作意欲が高まり、日本料理、イタリアン、中華料理の質的な
向上があるような気がします。これこそ「男の料理」と思ってみています。
生活ほっとモーニングで見ると各々の「レシピ」が載っていて、作り方のポイントが丁寧に書いてあります。
レシピどうりに作ってみますとそれなりにでき、楽しめます。
17期生の同好会にも「女と男の料理教室」があります。
この意味は「女と男が一緒に作る料理」なのか、「女の料理」「男の料理」なのかよくわかりません。
「そんなの関係ない」料理は料理といえばそれまでです。それなら料理教室でいいわけです。
「」女と男の料理教室」にお願いしたいことがあります。
レシピと作り方を載せ、味はどうだったかを同好会のホームページに書いてもらえませんか。
面白くなると思いますがどうでしょうか。

生活・野菜つくり
・ キャベツよりナメクジ這い出る春隣
・ ふと野性にかえり飼い猫春の風
・ 春芽吹きうながす雨か眠き午後
・ 春待たずブルートレイン姿消す
・ 水滴が額に落ちる春彼岸
・ 花粉舞う日の誘惑に布団干す
・ 日の温み布団にしみて山笑う
・ 霧晴れて深みましたる春の山
・ 下草を抜けば匂いの青きかな
・ そら豆の芯摘むことも教わって
・ 目の前にそびえる山に山桜
トンド焼
・ 火柱の風に煽られとんど焼
・ とんどの火雪巻き上げて天を向く
・ とんどの火竹はぜる音子の走る
・ とんど焼風向き変り降る火の粉
・ 激しさも竹倒るまでとんどの火
・ とんどの火薬缶(やかん)でわかす昼の酒
・ とんど焼しまいは焚き火ヤカン酒
海鼠(なまこ)
・ 海鼠食う男であって木偶の坊(でくのぼう)
・ 大寒の骨なき海鼠の硬さかな
・ 人の業身を硬うする寒海鼠
・ 海の香や寒の海鼠の噛みごたえ
・ 口に残る海鼠の匂い春立てり
認知症の義母
・ 木枯らしや認知の母の口が立ち
・ 認知症母のため息寒に入る
・ ナマケモノに似て着膨れの母老ゆる
・ 声荒ぐ認知の母につらい冬
冬至
・ 柚子一つぶっきら棒に冬至の湯
・ 山際に満月住めり冬至冷え
・ 鮟鱇や腹暖める燗の酒
・ 幼子は幼子の夢クリスマス
蟷螂(とうろう) 「かまきり」の異称
・ もう死ぬか蟷螂に日のあたりたる
・ 蟷螂の命彷徨う日の温み
鵯(ひよ)
・ 幾たびか鵯来て騒ぐ残り柿
・ 鵯の来て口にくわえし実南天
・ 目の前を鳥飛び立ちて冬ざれる
雪
・ 屋根に積む雪に照らされ朝の月
・ 紅茶舞う至福のときを小雪舞う
・ 闇の中楽しんでいる雪の音
野菜
・ 大根の青首伸びる長さかな
・ 大根の首伸ばし見る雪の山
・ そら豆の霜に打たれて右往左往
・ 焼いて食うねぎの甘さや寒安居
・ 寒の水大根洗い漬け終わる
冬銀河
・ 冬銀河蝋梅の香を風はこぶ
・ 冬銀河父星母星兄の星
・ 冴え渡る星は昔のまま光る
元旦
・ 元旦の重き新聞山光る
・ 後戻りできぬ壁あり去年今年
・ 初笑い持たぬ贅沢することも
布団
・ 裏返す布団の温み山眠る
・ 春の夢楽しんでいる羽根布団
冬鳥
・ 目白来る木の葉隠れに冬の庭
・ こがら来て冬ざれの庭明るうす
春一番
・ 春一番皺一本が顔に増え
・ スギ花粉春一番は鼻に吹き
叶谷史郎

